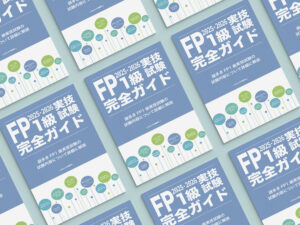FP2級に合格後は、FP1級合格を目指しませんか? FP1級試験勉強方法 スケジュール編
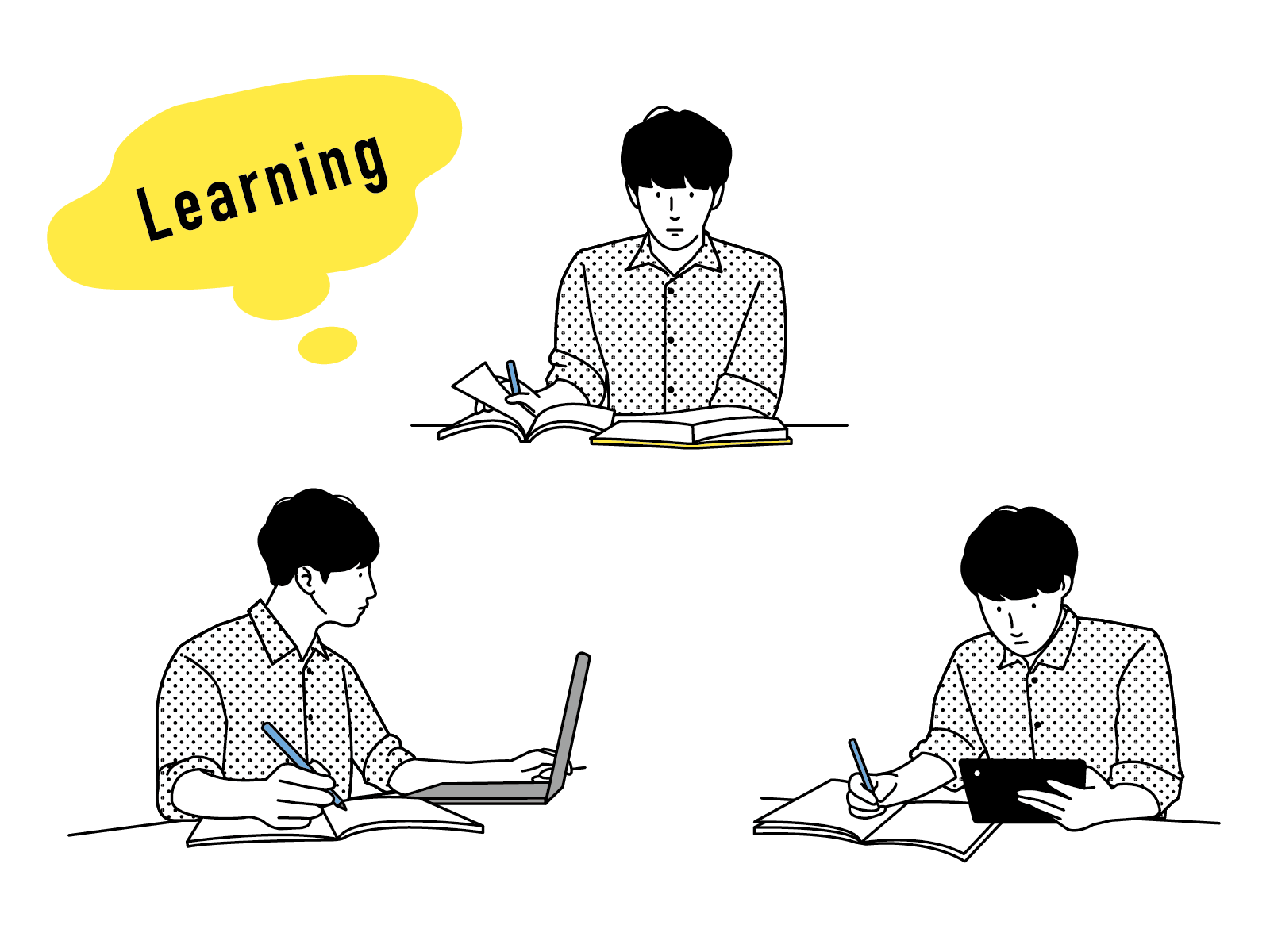
公開日 2021年10月13日 最終更新日 2025年6月19日
FP2級試験を合格した方で、このサイトにたどり着いたということは、FP1級試験にチャレンジしてみようとお考えではないでしょうか?
FP2級試験を合格した後は、
どうせなら1級まで目指そうかなぁ
1級受けるなら、せっかく覚えた知識を無駄にしないように、2級を合格直後の試験を受験した方がいいよ
などと、FP1級技能士合格にに手が届きそうな手応えを感じている方も多いでしょう。
一方で、
1級と2級とでは次元が違うよ
あんなの合格できるわけがない
というような意見を耳にすることも多いのですが、果たしてどうでしょうか?
FP1級試験と2級とでは、学習時間に差があり一般的に1級合格に要する学習時間は300時間程度と言われています。
仕事の傍での勉強が多くなるFP1級試験は、ペース配分と戦略がとても重要です。
綿密に戦略を練り、立案したら自分を信じて合格に向かって突き進むのみです。
結論を先に言うと「FP2級に合格できればFP1級も合格できます。FP1級試験を受験するなら、次に開催される試験を受験する」と言うことです。
目次
FP1級試験のスケジュールを確認しよう
FP1級試験を受験する意思が固まったら、いつの試験を受験するか受験日を決めましょう。
基本的には、FP2級合格後の次に開催される試験を受験する方がベストです。
理由は
- 2級の知識が活かせる
- 勉強の習慣がついている
- モチベーションが高い
- 合格の喜びと、2級に受かったんだから、1級も受かるんじゃないかと思う
他にもいろいろあると思いますが、とにかく次の試験を受験する方がベストです。
スケジュールは試験日程以外に、法改正など周辺情報もよく把握して逆算で立てることが重要です。
FP試験の年間スケジュールをまとめてみました。
プライベートの用事や、様々な事情で直後の試験を受験することが難しい場合も、まずは大まかな日程を確認しましょう。
FP1級試験年間スケジュール
| 月 | イベント |
| 1月 | 1級学科試験(法令基準日(前年10月1日) |
| 2月 | 1級実技試験 |
| 3月 | 年度末 |
| 4月 | 法改正 |
| 5月 | 1級学科試験(法令基準日:前年10月1日) |
| 6月 | 1級実技試験 |
| 7月 | |
| 8月 | 夏休み |
| 9月 | 1級学科試験(法令基準日:当年4月1日) |
| 10月 | 1級実技試験 |
| 11月 | |
| 12月 | クリスマス |
FP試験の法令基準日
| 試験日 | 2025年5月25日 | 2025年9月14日 | 2026年1月25日 |
| 法令基準日 | 2024年10月1日 | 2025年4月1日 | 2025年10月1日 |
| 試験日 | 2024年6月~2025年5月 | 2025年6月~2026年5月 |
| 法令基準日 | 2024年4月1日 | 2025年4月1日 |
1級実技試験については原則として試験日現在施行の法令等に基づくものとします。
ほとんどの法改正が4月に施行されますが、1級試験は最新の法改正部分が出題されることも多いので、試験日と法令基準日はチェックしておきましょう。
毎年4月の法改正を踏まえた、テキストや問題集が発売されるのが5月〜7月になります。
9月試験を1回目、1月試験を2回目、5月試験を3回目と捉えると実技試験までテキストを買い直す必要はなくなります。
2020年はコロナの関係で5月6月の試験が中止になったため、テキストや問題集を買い直したり、スケジュール変更や気持ちの切り替えが大変だったと思います。
FP1級学科試験は受験者数も年々増加傾向にあり、2018年度までは9月と1月の年2回開催でしたが、2019年度から5月にも実施されるよにになり、年3回受験できるようになりました。
これもFP1級技能士が世の中に認知されて、人気の資格になってきたからではないでしょうか?
最近の試験はコロナ禍の影響か、合格率が上がったので、
◯月の合格率が高いから、◯月がいいらしいよ。
前回合格率が高かったから、次回は難しくなるんじゃないかしら。
5月の受験でダメだったら、テキストを買い直す必要があるから9月からがいいよ。
など、いろんな意見を見かけます。
しかし、繰り返しますが、ベストは「次に申し込める試験を受験する」です。
ただし、300時間の勉強時間を確保できるスケジュールが組めればです。
勉強時間を確保することとモチベーションを維持する必要があるので、試験日まで十分な時間があった方がいい方もいれば、短期集中じゃないとモチベーションが続かない方もいると思います。
仕事やプライベートの予定を踏まえて、モチベーションが続く勉強時間の確保ができる試験日を決めましょう。
次に、試験日ごとのスケジュール例を考えて見ました。
5月に受験する場合のスケジュール
1月の試験で2級を合格し5月に1級を受験しようという方は、まずは現行版のテキストと問題集を買いましょう。
現行のテキストや問題集は、おそらく5月の試験以降は新年度版が発売され、内容が変わってしまいます。
改訂されているとはいえ、2回同じテキストを買うのはもったいないですよね。
次のテキストは買わない! このテキストで勝負する
というプレッシャーを掛けることができます。
それに、5月の試験は年金の計算など改正の影響が少ないので、2級で勉強をしてきた延長線上で受験できるのは有利だと思います。
9月に受験する場合のスケジュール
まず、現行版のテキストや問題集をお持ちの方は、新年度版のテキストが発売される5月〜7月までに、問題集を仕上げることを当面の目標に設定します。
次に新年度版のテキストを購入したら、試験日まで残り少ないですが問題集を3周以上は解きたいところです。
「問題集を何周もする」という話をすると、こんな質問をされます。
同じ問題を何度も解いて効果があるんですか?
過去に解いたことのある問題でも、何度も間違えてしまう問題や、一度解けても次が解けない問題がFP1級には必ずあります。
出題範囲がほぼ無限大の基礎編の問題を予想するのはかなり難しいですが、出題パターンが決まっている応用編なら、過去問や問題集を繰り返し説くことで予想可能だと思います。
回数を重ねると過去問で8割〜9割ぐらい正解することができるようになります。
これぐらいまで繰り返し問題を解くと、自分の解答パターンができるので、本番でも周囲の電卓の音に惑わされず、試験に集中できます。
過去問や問題集を、繰り返し何周も解くことで確実に実力が付くので、できれば毎日、継続して解くことをお勧めします。
1月に受験する場合のスケジュール
この時期で一番大変なのは勉強時間の確保です。
クリスマス、年末年始と、仕事やプライベートでも忙しくなる時期に、勉強時間を確保するのは大変だと思います。
しかし、世の中はこの頃ちょうど受験シーズン真っ只中なので、学生気分で何とか勉強時間を確保しましょう。
2級合格後すぐに1級にチャレンジする方は、学習時間が短く感じるかもしれません。
しかし、直前試験での2級合格者は、合格直後のテンションが上がった状態で1級の勉強ができるのを最大限に活かすべきです。
2級の能力者なら1、級を3ヶ月で勝負することは十分に可能です。
思い立ったらすぐ行動!
次の試験で合格を目指す!
2級と1級の試験分野は一緒なのです。
2級の試験範囲では出題対象にならなかった、細かいところまで出題されているだけの話です。(本当に細かいところまで出題されます)
したがって、2級合格での喜びは通過点だと思い、チャレンジャーの気持ちで取り組むことが大切です。
3級から受験してきた方は2級を受験する際に、3級受験の時に勉強した知識がそのまま通用するので、同じ感覚で2級から1級への受験を捉えてしまうかもしれませんが、まったく別物と捉えておいた方が賢明です。
慌てずに良書のテキストと問題集を徹底的にやり込み覚え込むこと
何月の試験を受験する場合でも、基本的なFP受験に対する心構えやコツみたいなものは、2級合格までの道のりで掴んでいるので大丈夫ですが、2級までの知識でいきなり問題集を解くことから始めてしまうと、戸惑うことが多いと思います。
なぜかというと、同じ分野の問題でも内容の深さや広さが1級と2級ではかなり違います。
ざっとでもいいので、テキストにさっと目を通した後の方が、解き始めても心が折れないと思います。
まずは、テキストを「軽く全体像やレベル感を掴む」「知らない部分を補完する」「忘れていることを思い出す」感じで読んでみることから始めると、1級と2級の違いが感じ取れると思います。
この時点ではまだ「暗記」の必要はありません。
1級の出題範囲は、そもそもの覚える分量がものすごく多いので、マーカーをひいたりノートにまとめるのは、問題集に取り掛かり、どのように出題されるかをつかんでからのほうが、無駄な暗記やノート作成に時間を使わずに効率的です。
あくまでも目的は「軽く全体像やレベル感を掴む」「知らない部分を補完する」「忘れていることを思い出す」ことなので、2週間ぐらいでテキストを読んでしまいます。
合格への最短ルートは、きちんと1級に対応したテキストを習熟して、問題集でその精度を上げていくことが近道です。
2級を合格した方であれば、言葉の意味は理解できるので、FPの基礎学力は身についています。
2級までの学習で身についた知識レベルを、1級のレベルに引き上げるだけです。
【悲報】きんざいが制作していたFP受験対策に関する書籍は、今後制作されません。

2023年4月1日に、金融財政事情研究会がきんざいと経営統合したために、きんざいが制作していたFP受験対策本は、今後制作しないとのことです。
では、テキストは何を買ったらいいのか?
2025-2026 1級FP技能士(学科)合格テキスト (2025-2026年版 国家資格ファイナンシャル・プランニング技能検定1級受検対策シリーズ)
全国の金融機関でFP受検研修に使用されています。受検指導に精通した講師陣による、FP技能検定1級合格に必須の全6課目の項目を厳選したテキストです。
【梶谷美果監修、ほんださん特別協力の強力タッグ】
1級FP技能士(学科)合格テキスト、1,000ワード超の索引で学習効率アップ対策問題集の監修者で20年以上のFP講師歴を誇る梶谷美果の監修に加え、2024年度版から新たに、FP業界トップとなる18万人超のYouTubeチャンネル登録者数を有する「ほんださん」(本多遼太朗)が特別協力してお届けする、FP1級学科試験対策の決定版です!出典:Amazon商品ページより抜粋
- この1冊だけで、1級学科試験の合格レベルの知識をインプットすることができるよう、長年、FP1級学科試験受検対策の研修講師を経験している者たちが知恵を出し合って、工夫して執筆しました。
- この試験では、いわゆる超難問も出題されますが、そのような問題すべてに正解するための学習は必要なく、定番問題やその類題を確実に正解できるような学習をすることが合格の秘訣であり、その点を重視したのが本書です。
- 定番問題には、「応用編」だけでなく「基礎編」でも計算問題が多くみられます。本書では、インプット学習だけではなく、知識を学んだすぐ後にアウトプット学習ができるよう、計算例や「応用編」対策としての計算問題を数多く盛り込みました。
- 本書と合わせて、『受検対策講義映像』『対策問題集』『対策模擬試験(基礎編・応用編)』を活用されることをお薦めします。
精選問題解説集も販売されません
合格ターゲットと同じく2023年4月1日に、金融財政事情研究会がきんざいと経営統合したために、きんざいが制作していたFP受験対策本は、今後制作されないので精選問題解説集も販売されません。
では、問題集は何を買ったらいいのか?
そこで、僕が実技試験対策本のKindle版とセット版を制作しました。
2025-2026 1級FP技能士(学科)対策問題集 (2025-2026年版 国家資格ファイナンシャル・プランニング技能検定1級受検対策シリーズ)
全国の金融機関のFP受検研修で教材として使用されています。過去の出題問題から厳選した問題に手を加え、詳しい解説付きで掲載しています。効率的な学習が可能です。
出典:Amazon商品ページより抜粋
- 本書『1級FP技能⼠(学科)対策問題集』は、『1級FP技能⼠(学科)合格テキスト』で学習した知識を、効果的にアウトプットできるように編集しています。
- 過去に出題された本試験問題を徹底的に分析し、受検⽣がぜひ解けるようにしておきたい問題を厳選しました。
- 本書とテキストを何往復もすることで、知識や問題の解法が定着して理解度が増していきます。
- 本試験では、名称の意味とは異なり、「基礎編」の⽅が難易度は⾼く、「応⽤編」の⽅が難易度は低くなっているため、「応⽤編」で⾼得点を獲得しなければなりません。そのためには、本書において分野ごとにまず先に「応⽤編」の問題から解いて、マスターしていくことをお勧めします。
残念ながら、1級に関しては「楽して〜」とか「効率的に〜」などとは考えず、正攻法で向かっていく姿勢が大切です。
FP1級技能士とは、過去に2万人弱程度しかいないFPの最高峰資格です。
延べ2万人弱といっても初期の合格者は、もう現役かどうかもわかりませんし、実際に活躍しているFP1級技能士は思いのほか少ないのが現状です。
そんな希少な資格ですので、小手先の技術では通用しません。真正面から正々堂々とねじ伏せる姿勢で突破していきましょう。
過去問ですが、基礎編は2年以上前の過去問は古いのでやりませんでした。
過去問を解く目的は、合格ラインをクリアしたかを図るためではなく、50問を連続して解く集中力の強化と、本番の試験同様に、様々な分野の知識を次から次に呼び起こすトレーニングをするためです。
基礎編は4択問題が50問出題されるので、実質200個の選択肢を判別することになり、問題文を読むだけでも思い込みや勘違いで読んでしまうこともあります。
それを防ぐために、過去問で本番試験の感覚を掴んでおきたかったのと、出題項目は6分野に一応分かれているものの、特にタックスなどは全分野に関係してくるので、分野にとらわれず知識を呼び起こすトレーニングをしておくことで、勘違いを防ぐことができます。
FP1級試験は検定試験ですので、合格ラインをクリアすることができれば合格です。
基礎編と応用編で合わせて120点以上の合格ラインをクリアすることが、最大の目標になりますので、しっかり戦略を立てて取り組むことが重要です。
FP1級試験に合格すると、沢山のいいことがあります。
- 金融機関等にお勤めの方なら周囲から一目置かれ、仕事がやりやすくなることは間違いない!
- 昇進のチャンスもあるはず
- FPとして独立や開業も現実的になる
- 独立・開業じゃなくても副業で収入を得るチャンスが広がる
- 勉強する習慣と自信がつき、他の難関試験にチャレンジしたくなる
などなど、FP1級に合格すると可能性が無限に広がります。
私が合格したので、誰にでも合格のチャンスはあります。
2級合格も素晴らしいですが、もうひと頑張りしてみませんか?
ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Xにてお知らせください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、FP1級技能士試験のご参考になれば幸いです。