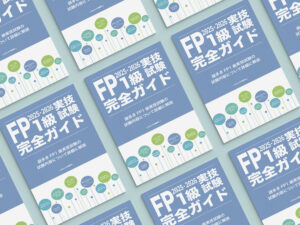面接試験会場を想定したFP1級実技試験の傾向と対策

公開日 2021年5月29日 最終更新日 2025年6月19日
実技試験の合格率は80%以上で、合格率10%の学科試験と比べると簡単そうに見えますが、決してそんなことはありません。
過去問を見ていただければ一目瞭然ですが、初見でスラスラ答えられるでしょうか?
私も学科合格直後に過去問を見たときは、問題を解くどころか、何をどうしていいのか全くわかりませんでした。
ファイナンシャルプランニング技能検定 1級実技試験結果
|
試験日 |
学科/実技 |
受験申請者数 |
受験者数 |
合格者 |
合格率 |
|
2025.02 |
実技 |
815 |
794 |
661 |
83.25% |
|
2024.09 |
実技 |
485 |
475 |
419 |
88.21% |
|
2024.06 |
実技 |
573 |
554 |
458 |
82.67% |
|
2024.02 |
実技 |
732 |
698 |
614 |
87.96% |
|
2023.09 |
実技 |
213 |
196 |
157 |
80.10% |
|
2023.06 |
実技 |
761 |
737 |
625 |
84.80% |
|
2023.02 |
実技 |
771 |
754 |
649 |
86.07% |
|
2022.09/10 |
実技 |
499 |
474 |
401 |
84.59% |
|
2022.06 |
実技 |
760 |
742 |
638 |
85.98% |
|
2022.02 |
実技 |
1,203 |
1,119 |
961 |
85.88% |
|
2021.09/10 |
実技 |
1,391 |
1,341 |
1,142 |
85.16% |
|
2021.06 |
実技 |
1,146 |
1,066 |
909 |
85.27% |
|
2021.02 |
実技 |
1,616 |
1,521 |
1346 |
88.49% |
|
2020.09/10 |
実技 |
815 |
798 |
689 |
86.34% |
|
2020.02 |
実技 |
730 |
710 |
603 |
84.92% |
|
2019.10 |
実技 |
543 |
521 |
433 |
83.10% |
|
2019.06 |
実技 |
720 |
699 |
599 |
85.69% |
|
2019.02 |
実技 |
809 |
783 |
677 |
86.46% |
|
2018.06 |
実技 |
1,124 |
1,096 |
936 |
85.40% |
|
2018.02 |
実技 |
793 |
775 |
670 |
86.45% |
|
2017.06 |
実技 |
852 |
830 |
718 |
86.50% |
|
2017.02 |
実技 |
408 |
392 |
331 |
84.43% |
|
2016.06 |
実技 |
810 |
789 |
649 |
82.25% |
|
2016.02 |
実技 |
785 |
763 |
618 |
80.99% |
FP1級実技試験を難しくしている要因の一つに、面接試験だということがあります。
学科試験は問題を熟読し考えて解答する、もしくは、わからない問題は飛ばすこともできます。
面接試験は口頭試問です。
「質問されたことを答える」
考える時間は一瞬で、わからない問題を飛ばして最後に答えることもできません。
情報量も少なく不安なことが多いFP1級実技試験。しっかりと対策をしなければ20%の不合格者になってしまいます。
受験料も28,000円もしますし、受験会場も少ないため(なぜか西日本に受験会場が集中しています)交通費や宿泊を含めた受験費用は10万円を超える場合もあります。
難関の学科試験を突破し、それなりの支出をして適当に勉強して受験するのはもったいないですよね。
私なりに実技試験の傾向と対策を考えてみましたのでご紹介します。
【悲報】きんざいが制作していたFP受験対策に関する書籍は、今後制作されません。

2023年4月1日に、金融財政事情研究会がきんざいと経営統合したために、きんざいが制作していたFP受験対策本は、今後制作しないとのことです。
では、テキストは何を買ったらいいのか?
実技試験対策本をKindleで出版しました
きんざいが制作していたFP受検対策に関する書籍は、今後制作・販売されません。
そこで、僕が実技試験対策本をKindleで出版しました。
動画で学習したい場合はFP1級実技試験対策講座がお薦めです。

FP1級実技試験完全ガイドの活用ポイント

大まかな実技試験での面接の流れを説明すると、
1
設例を読む
2
質問を受ける
3
回答する
4
回答に対するツッコミ
追加質問
という流れで面接が進んでいきます。
1設例を読む
設例を読む時間は15分間です。
私が受験した時は受験者が待機している部屋の隅に机が2つあり、Part1の受験者とPart2の受験者が一人づつ呼ばれ設例を読みます。

設例を読む時間がとても重要です。過去問題集を読んでもわかると思いますが、質問されることは設例に書かれていることがほとんどなので、設例をしっかり読むことができれば質問される内容が想定できます。
質問内容を想定することができれば、設例の用紙にメモをすることは可能なので思いつく限りの回答をメモします。
ここでトレーニングすることは、設例をよく読むことです。
設例をよく読むなんて当たり前だと思われるでしょうが、設例が細かくて文章も長いので見落としや勘違いすることがあります。
設例を読み、理解して、質問を想定して、回答を考えて、メモをするということが15分でどれぐらいできるのか一通りの作業を終えるトレーニングをしていく必要があります。
回答のヒントは設例に書いてあります。重要な情報を見落とさないためにも「FP技能検定1級実技(資産相談業務)対策問題集」の設例を隅々まで読み込むことがポイントです。
2質問を受ける

設例を読む15分間で、冷静に事例と問題点を把握し、出題意図を掴み、聞かれることをシミュレーションし、想定問答が固まったら面接室の前で待機します。
心の準備ができたらノックして入室です。
落ち着いて自己紹介をした後、質問を受けます。
私が受験した時は、コロナ対策をした状態での受験だったので、マスクをつけパーテーション越しでの面接でした。
事前に説明があると思いますが、質問が聞き取りにくい場合は遠慮せず「聞き取れなかったので、もう一度質問をお願いします」と再度、質問してもらいましょう。
間違っても、聞こえたふりをして曖昧な答えはしないようにしましょう。
「FP技能検定1級実技(資産相談業務)対策問題集」の想定される質問事項を読むと、どの設例にも共通する質問事項や提案例があります。
共通する提案例の解説を「FP1級実技試験完全ガイド」では項目ごとにまとめていますので、よく聞かれる質問に対しての対策が効率的にできます。
3回答する
皆さんもお仕事などで「人前での説明がうまくいかずに焦ってしまった」「相手から要領を得ない下手な説明を受け何度も聞き返した」という経験はありませんか?
これらは面接試験の大敵です。
これを防ぐためには、自分の言葉で説明する訓練はかかせません。
本番では、おそらく想像以上に緊張すると思います。
いい大人になると、面接試験のような独特の緊張感を味わう機会は減りますので、久々の大舞台では舞い上がってしまいがちです。
テキストを読み、頭の中で答えてみて、解説を読むというよりも、書いて学習することをお勧めします。
回答を書いて、その文を解説で読みつつ添削することで、どの文言を答えていて、何が説明不足か明確にしていきます。
また、ノートに書くことで見直したときに自分が忘れがちなポイントが一目でわかるようになります。
書くときのポイントは、口語調で書きます。頭ではわかっていても、相手に説明することは思いのほか難しく、わかっているのに、うまく伝わらないということがないように、書いた後は誰かに話して説明してみたり、ボイスレコーダーで自分の回答を聞いてみるのも効果的です。
4回答に対するツッコミ 追加質問
FP1級実技試験の最難関ポイントが「回答に対するツッコミ 追加質問」への対応です。
どういうことかというと
円満な遺産分割を行うために、遺言書を作成することを提案します。
遺言書には、どのような種類の遺言書がありますか?
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
自筆証書遺言保管制度について教えてもらえますか?
ん〜、たしか…法務局で保管することができる制度です。
保管の申請ができる遺言保管所はどこの法務局でもいいですか?
ん〜。調べて回答します…。(汗)
せっかく回答できて、ほっとしたのも束の間。
質問者が「その制度はどんな種類がありますか?」「どのような方に適用できますか?」と回答に対して追加で質問したり、ツッコんで深掘りしてくることがあります。
「FP1級実技試験完全ガイド」に書いてあるくらいの説明は求められると想定した方がいいでしょう。
正解ではなく、FPとして答えるべき内容を答える
「ちょっと何いってるかわからないですけど。」
とツッコミを入れたくなるところですが、どういうことかというと。
相続税額を軽減するためにはどのようなことを提案しますか?
ん〜。
退職金を限度額まで出すと、債務超過や流動性が低下し有利子負債やフローによっては融資が受けにくくなり、そもそもの事業に影響をあたえそうだなぁ
相続税の軽減だからと法人資産を引っ張ったりすると継業に大きな影響を与えかねません。豊富な実務経験がある方は、模範回答よりいい提案ができる可能性がどの設例でもあります。
本来、的確に提案するのであれば、設例程度の情報量では答えられるものではありません。
だからと言って、「情報が少なすぎて答えられるません」とは言えませんし、テキストにないようなクセの強い独特の答えを言ってしまうと、不正解になるのではないでしょうか。
FP試験は、FP1級技能士としての知識レベルを問うものです。合格するためには設問者が求める回答をすることです。
要は、「あなたが思うベストと考える答え」ではなく「FPとして答えるべき内容」を答える必要があります。
FP1級を受験ししようと思う方は、勉強熱心で実務経験も豊富なお客様のことを第一に考える方だと私は思います。
だからこそ、注意しなければいけない点があることを知っていただけたらと思います。
ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Xにてお知らせください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。皆さんのFP1級技能士試験合格を願っています。