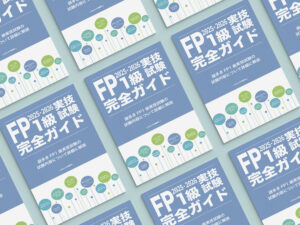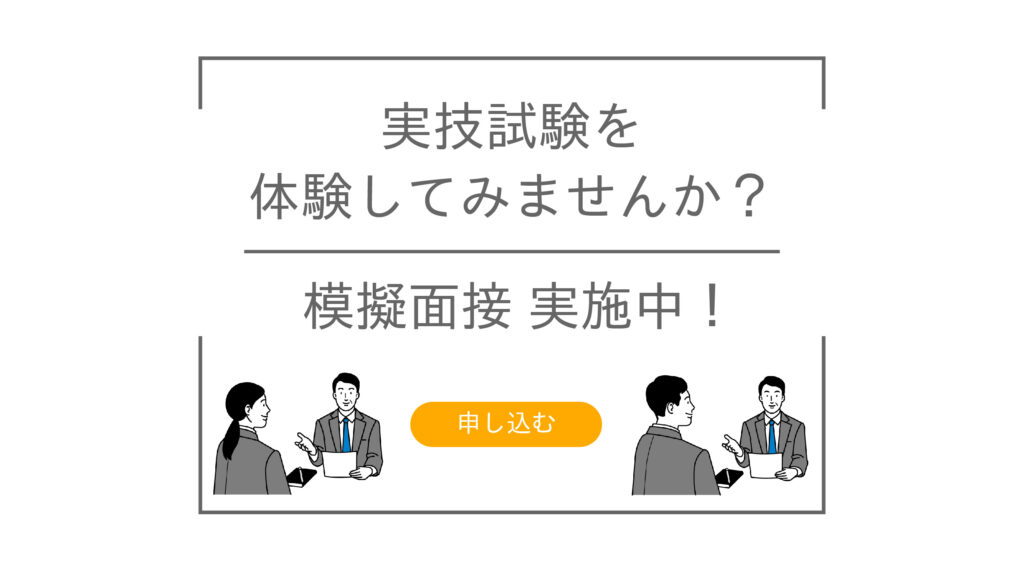2024年9月8日実施 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験(応用編)過去問解説《問60》
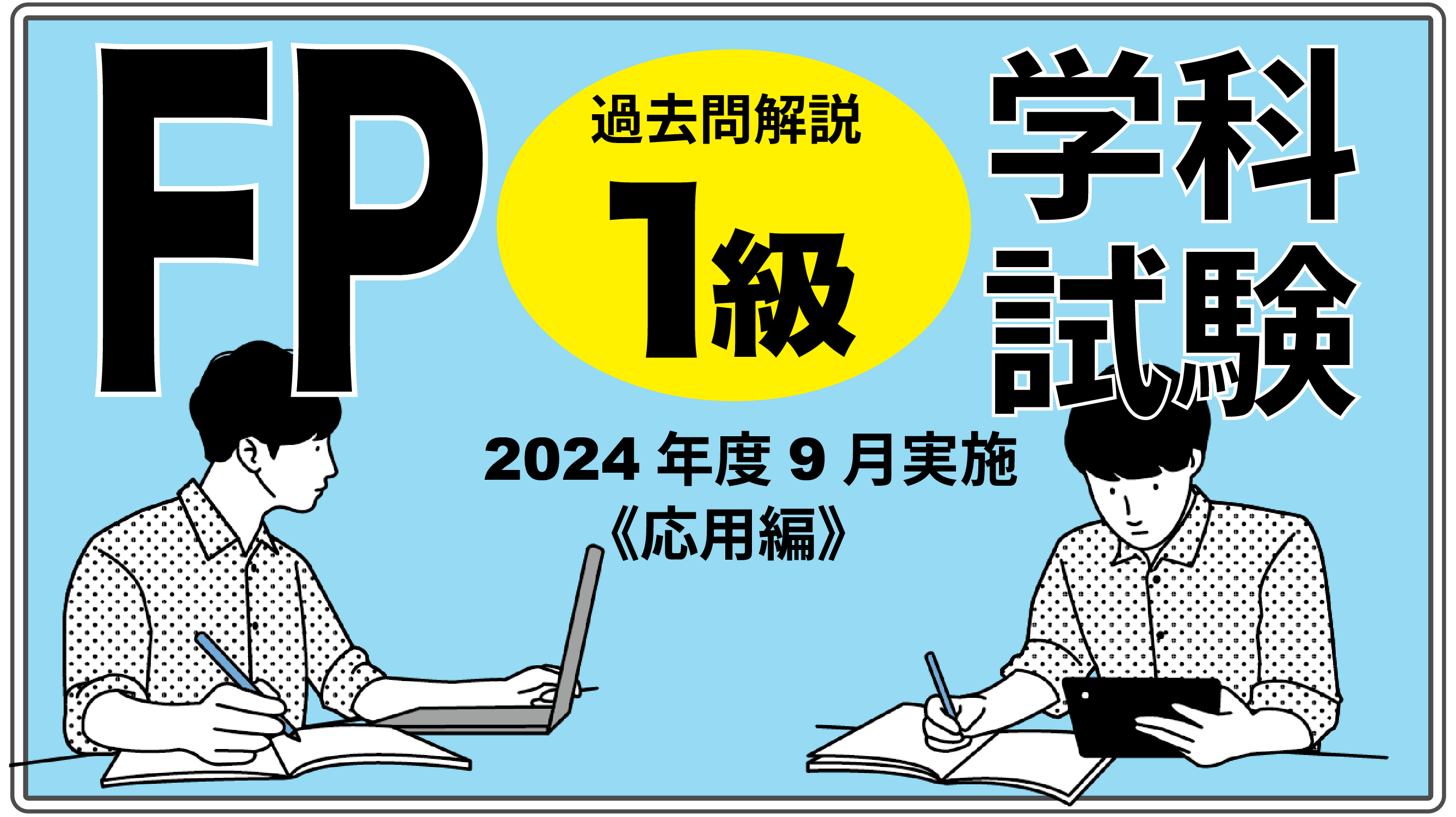
公開日 2024年12月13日 最終更新日 2024年12月18日
《設 例》
|
社員のAさん(50歳)は、K市内にある自宅で妻と2人で暮らしている。自宅はAさんが5年前に父親の相続により取得したものであり、建築から40年が経過した建物は、所々に傷みが目立つようになってきた。自宅の建替えも検討したが、現在住んでいる場所よりも交通の便のよい地域に引っ越したいと考え、自宅を売却するつもりでいる。 Aさんは、引っ越し先を探すなかで、売りに出されていた甲土地に興味を持ち、甲土地を購入して、その上に自宅として戸建て住宅を建築することを検討している。 甲土地の概要は、以下のとおりである。
(注)
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
建築基準法の道路および固定資産税に関する以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
〈建築基準法の道路〉
- 「都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( ① )m以上接していなければなりません。この建築基準法上の道路とは、公道や私道という分類に関係なく、原則として、次のものをいいます」
- 建築基準法第42条第1項
次のいずれかに該当する幅員( ② )m以上のもの
42条1項1号道路 道路法による道路(国道、都道府県道等の道) 42条1項2号道路 都市計画法や土地区画整理法等による道路(土地区画整理や宅地開発等で築造された道) 42条1項3号道路 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する道 42条1項4号道路 道路法や都市計画法等による新設等の事業計画のある道路で、( ③ )年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの 42条1項5号道路 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法や都市計画法等によらないで築造する一定の基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその□□□の指定を受けたもの(一般に( ④ )道路と呼ばれる) - 建築基準法第42条第2項
42条2項道路 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員( ② )m未満の道で、特定行政庁の指定したもの
〈固定資産税〉
- 「固定資産税は、1月1日現在、土地、家屋等の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者に課されます。固定資産税の税額は、課税標準額に税率を乗じて得た額とされ、標準税率は( ⑤ )%とされていますが、地方公共団体によって税率が異なることがあります。なお、住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格の( ⑥ )分の1の額とする特例があります」
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
〈答〉 ① 2(m) ② 4(m) ③ 2(年) ④ 位置指定(道路) ⑤ 1.4(%) ⑥ 6(分の1)
Ⅰ 建築基準法の道路
建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条で定義されている道路で、建築物を建てる際に利用される敷地が2m以上接していなければならない道路です。
建築基準法上の道路には、次のような種類があります。
- 道路法(一般国道、県道、市道等)による道路で幅員4m以上の道路
- 都市計画法、土地区画整理法等による道路で幅員4m以上の道路、開発行為による道路
- 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際(基準時)に、現に存在する道で、基準時に道路としての効用を果たし得る程度の実態を備えており、かつ、幅員が4m以上あるもの(私道も含まれます)
- 道路法、都市計画法等による事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
- 土地を建築物の敷地として利用するため、土地所有者等が築造する道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けた幅員4m以上の道路
① 2(m)
- 建築基準法第43条第1項により、建築物の敷地は建築基準法上の道路に「2m以上接する」必要があります。
② 4(m)
- 建築基準法第42条第1項の道路の幅員は原則として「4m以上」と定められています。
③ 2(年)
- 42条1項4号道路では、事業計画の実施が「2年以内」とされているものを指します。
④位置指定(道路)
- 42条1項5号道路は、建築基準法令等で定める基準に適合する道路で、土地の所有者が築造するにあたって特定行政庁から位置の指定を受けたものを指します。一般に位置指定道路と呼ばれ、特定行政庁に申請することで位置指定が行われ、建築基準法上の道路として認められます。
Ⅱ 固定資産税
固定資産税は、課税標準である固定資産税評価額に、1.4%(標準税率)を、都市計画税では0.3%(制限税率)の税率を掛けて税額を出します。
ただし、固定資産税の標準税率は地方税法によって市町村ごとに異なる税率を定めることができるため、全国一律ではありません。
住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200 ㎡以下の小規模住宅用地の場合、固定資産税評価額が1/6になり、都市計画税の課税標準額は、固定資産税評価額の1/3の額となります。
なお、200㎡を超える一般住宅用地の場合は、固定資産税の課税評価額が1/3 、都市計画税における固定資産税評価額は2/3になります。
⑤ 1.4(%)
- 固定資産税の標準税率は原則として「1.4%」です。
⑥ 6(分の1)
- 小規模住宅用地(200㎡以下)では、課税標準額が「6分の1」に軽減されます。