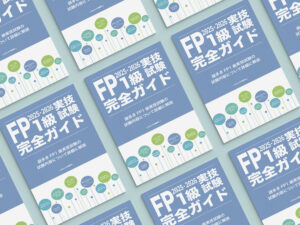FP1級試験問題 略式別表四の問題を解説します
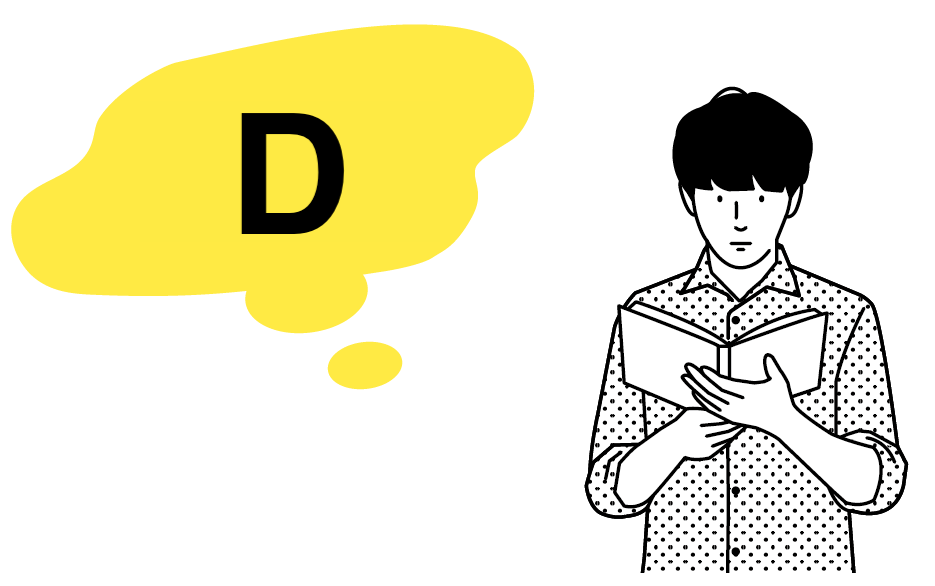
公開日 2021年10月12日 最終更新日 2022年4月25日
FP1級試験の勉強を始めても、出題範囲が広すぎて何から手をつけていいのかわからなかったり、せっかく覚えても忘れてしまい心が折れることってありませんか?
このサイトでは、私が実践し得点が倍増した勉強方法についてご紹介します。
今回はD.分野 タックスプランニングから略式別表四の問題です。
略式別表四の計算問題は、FP1級試験の応用編で過去8回のうち5回出題されていて、最近では3回連続で出題されています。
応用編のタックスプランニングの問題は事業所得の計算から課税総所得金額を求める白色・青色申告と、略式別表四から法人税額を求める問題のどちらかが出題されるので、白色・青色申告と略式別表四の計算式は完璧に覚えておく必要があります。
略式別表四のポイントは設例をしっかり読むことです。
設例をしっかり読むと計算しなくても解答できる問題もあるので、落ち着いて設例を読み込みましょう。
略式別表四の問題を間違えると、次の法人税額の問題も間違えることになるので注意しましょう。
応用編は、模範解答だけでなく総合的な観点を考慮して採点されます。配点は公表されていませんので独自の配点方法で計算します。
- 応用編の100点満点を5分野(5問)で均等に割り、1分野(1問)を20点とします。
- 穴埋め問題を1問1点とし、20点から穴埋め問題の数を引いた残りの点数を、計算問題の配点としています。
- C分野の財務諸表を説明しながら計算する問題、D分野の略式別表四の計算問題は、1問1点とします。
【例】[第1問]《問51》穴埋め問題8問(8点) 《問52》穴埋め問題6問(6点) 《問53》計算問題2問(20点−8点−6点=6点)
| 《問57》 | 《問58》 | 《問59》 | ||||
| 2022年1月 |
|
6点 |
|
4点 |
セルフメディケーション税制・医療費控除の計算 住宅借入金等特別控除の説明 |
10点 |
| 2021年9月 |
|
7点 |
|
5点 |
|
8点 |
| 2021年5月 |
|
8点 |
|
6点 |
|
6点 |
| 2021年1月 |
|
8点 |
|
6点 |
|
6点 |
| 2020年9月 |
|
7点 |
|
7点 |
|
6点 |
| 2020年1月 |
|
6点 |
|
8点 |
|
6点 |
| 2019年9月 |
|
7点 |
|
7点 |
間違っている選択肢を選び適切な内容に訂正する
|
6点 |
| 2019年5月 |
間違っている選択肢を選び適切な内容に訂正する
|
8点 |
|
6点 |
|
6点 |
■略式別表 ■白色申告 ■青色申告
FP1級学科試験 応用編《D分野の計算問題》 (2022年1月開催〜2019年9月まで 7回分を集計)
それでは、過去問を解きながら解説していきます。
略式別表四の問題 2021年9月12日試験 応用編 《問57》
《設例》のX社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄①~⑦に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。
〈条件〉
- 設例に示されている数値等以外の事項については考慮しないものとする。
- 所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得の金額が最も低くなる方法を選択すること。
〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉 (単位:円)
区 分 総 額 当期利益の額 5,199,370 加算 損金経理をした納税充当金 ( ① ) 減価償却の償却超過額 ( ② ) 役員給与の損金不算入額 ( ③ ) 役員退職給与の損金不算入額 ( ④ ) 小 計 *** 減算 減価償却超過額の当期認容額 ( ⑤ ) 納税充当金から支出した事業税等の金額 730,000 小 計 *** 仮計 *** 法人税から控除される所得税額(注) ( ⑥ ) 合 計 *** 欠損金又は災害損失金等の当期控除額 0 所得金額又は欠損金額 ( ⑦ ) (注)法人税額から控除される復興特別所得税額を含む。
《設例》
小売業を営むX株式会社(資本金30,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2022年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである〈資料〉
- 減価償却費に関する事項
当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、器具備品の減価償却費は3,000千円であるが、その償却限度額は2,800千円であった。一方、建物の減価償却費は5,800千円であるが、その償却限度額は6,000千円であった。なお、前期からの繰越償却超過額が当該建物について350千円ある。- 役員給与に関する事項
当期において、取締役のAさんに対して支給した役員給与は、2021年4月分から2021年11月分までは月額800千円であったが、2021年12月分から2022年3月分までは月額1,000千円に増額した。このAさんに対する役員給与について、増額する臨時改定事由は特になく、X社は所轄税務署長に対して事前確定届出給与に関する届出書を提出していない。- 役員退職金に関する事項
当期において、退任した取締役のBさんに対して役員退職金を35,000千円支給した。この役員退職金の税法上の適正額は、最終報酬月額800千円、役員在任期間15年、功績倍率2.5倍として功績倍率方式により算定した金額が妥当であると判断されたため、支給額のうち功績倍率方式により計算された適正額を上回る部分については、別表四において自己否認を行うことにした。- 税額控除に関する事項
当期における「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」に係る税額控除額が250千円ある。- 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
- 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額30千円・復興特別所得税額630円および当期 確定申告分の見積納税額2,500千円の合計額2,530,630円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は2,500千円である。
- 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は730千円である。
- 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
- 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 1級学科試験、1級実技試験(個人資産相談業務) なお、当サイトの管理人は一般社団法人金融財政事情研究会のファイナンシャル・プランニング技能士センター会員のため許諾申請の必要なく試験問題を利用しています。参考:技能検定試験問題の使用について
老齢年金の問題 2021年9月12日試験 応用編 《問57解答と解説》
①損金経理をした納税充当金額
〈資料〉5. 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項をチェック
“損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額30千円・復興特別所得税額630円および当期確定申告分の見積納税額2,500千円の合計額2,530,630円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は2,500千円である。”
《解説》
納税充当金額は当期に確定した法人税を翌期の支払いに充てるために計上
確定申告の見積納税額、未払法人税の期末残高=①2,500,000(円)
損金経理をした納税充当金=「未払い法人税等」の金額
納税充当金とは、決算時に見積計上する法人税・住民税・事業税のことなので、「未払い法人税等」と同じ意味になります。
資料の中から「未払い法人税等」の金額を記入するだけなので、計算する必要はありませんね。
②減価償却の償却超過額
〈資料〉1. 減価償却費に関する事項の償却限度額を超えている減価償却費をチェック
“当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、器具備品の減価償却費は3,000千円であるが、その償却限度額は2,800千円であった。一方、建物の減価償却費は5,800千円であるが、その償却限度額は6,000千円であった。なお、前期からの繰越償却超過額が当該機械装置について350千円ある。”
《解説》
償却限度額を超過した減価償却費は損金不算入
減価償却費−償却限度額=減価償却費の償却超過額
3,000,000円−2,800,000円=②200,000(円)
法人税の所得金額の計算上、損金算入できる減価償却費は、償却費として損金経理した金額のうち、その資産について選択した償却方法によって計算した償却限度額に達するまでです。
つまり、償却限度額を超過する部分は損金に算入することができません。
③役員給与の損金不算入額
〈資料〉2. 役員給与に関する事項の給与増減時期、臨時改定事由、事前確定届出の提出をチェック
“当期において、取締役のAさんに対して支給した役員給与は、2021年4月分から2021年11月分までは月額800千円であったが、2021年12月分から2022年3月分までは月額1,000千円に増額した。このAさんに対する役員給与について、増額する臨時改定事由は特になく、X社は所轄税務署長に対して事前確定届出給与に関する届出書を提出していない。”
《解説》
定期同額給与では、事業年度開始から3ヶ月以上経過した増額改定の場合、改訂前の定期同額給与は損金算入できますが、資料によると、臨時改定自由も特になく、事前確定届出給与に関する届出書も提出していないので、改定後の増額部分は損金算入が認められません。
1,000,000円(増額後)−800,000円(増額前)=200,000円
200,000円×4ヶ月(2021年12月〜2022年3月)=800,000円
法人が役員に対して支給する給与の額については、法人税法に定める「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかに該当しなければ、損金算入できません。
定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとに支払われる給与で、事業年度内で毎月同じ金額が支払われる給与です。
ただし、事業年度開始後3ヶ月以内の改定では、定期同額給与に該当されます。
3ヶ月経過後に増額改定された場合は、改定後の増額部分は損金算入が認められません。
減額改定した場合は、改訂前の給与のうち、改定後の金額を超える部分(減額した部分)が損金不算入になります。
事前確定届出給与とは、事前に役員へ支払う時期と支給額を定め、届出期限までに税務署長に届出ているもののことです。
業績連動給与とは、業績に関する指標を基礎として算出される、役員賞与などのことです。
④役員退職給与の損金不算入額
〈資料〉3. 役員退職金に関する事項の償却限度額を超えている減価償却費をチェック
“当期において、退任した取締役のBさんに対して役員退職金を35,000千円支給した。この役員退職金の税法上の適正額は、最終報酬月額800千円、役員在任期間15年、功績倍率2.5倍として功績倍率方式により算定した金額が妥当であると判断されたため、支給額のうち功績倍率方式により計算された適正額を上回る部分については、別表四において自己否認を行うことにした。”
《解説》
支給した退職金のうち、適正額以上に支給した金額は損金の額に算入できません。
・役員退職金の適正額(功績倍率方式により算定)
最終報酬月額×役員在任期間×功績倍率=役員退職金の適正額
800,000円×15年×2.5=30,000,000円
・役員退職金の損金不算入額
支給した退職金−役員退職金の適正額
35,000,000-30,000,000=④5,000,000(円)
役員退職金について、業績連動給与に該当しないものは損金算入できますが、不相応に高額な場合には、高額である部分については損金算入できません。
一般的に、不相応に高額かどうかを判断する基準として、功績倍率法が用いられます。
【功績倍率法】
役員退職金の適正額=最終報酬月額×役員在任期間×功績倍率
役員退職給与の損金算入時期については、原則として、その役員の退職時に直ちに損金算入することはできません。
退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度において、損金算入します。
⑤減価償却超過額の当期認容額
〈資料〉1. 減価償却費に関する事項の償却限度額を超えている減価償却費をチェック
“当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、器具備品の減価償却費は3,000千円であるが、その償却限度額は2,800千円であった。一方、建物の減価償却費は5,800千円であるが、その償却限度額は6,000千円であった。なお、前期からの繰越償却超過額が当該機械装置について350千円ある。”
《解説》
当期の減価償却費が償却限度額に達していない場合、同一科目の繰越償却超過額は当期に損金算入できる
償却限度額−減価償却費=当期認容可能額
6,600,000円−5,800,000円=200,000円
350,000円>200,000円 減価償却超過額の当期認容額=⑤200,000円
減価償却費が償却限度額に満たない場合、前期以前に償却超過額が生じている資産は、償却不足額の範囲内で、繰越償却超過額が認容され、当期の損金に算入されます。
⑤法人税額から控除される所得税額および復興特別所得税額
〈資料〉5. 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項をチェック
“⑴ 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額30千円・復興特別所得税額630円および当期確定申告分の見積納税額2,500千円の合計額2,530,630円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は2,500千円である。
⑶ 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。”
《解説》
〈資料〉5. ⑶で「所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除する」と書かれている。
30,000円+630円=⑥30,630(円)
〈資料〉に「所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除する」と書かれているので、資料の「所得税額と復興特別所得税額」の金額を合計するだけですね。
⑦所得金額又は欠損金額
《解説》
略式別表四の加算、減算は文字通り足して引くことですが、法人税額から控除される所得税額は、控除なのに加算するので気をつけましょう。
当期利益の額+加算項目の小計−減算項目の小計+法人税額から控除される所得税額
5,199,370円+8,500,000円−930,000円+30,630円=⑦12,800,000(円)
〈学習のポイント〉
略式別表四の問題はパターンが決まっている問題が多く、慣れてしまうと得点源になる問題なので繰り返し学習しましょう。
2022年1月の試験では、減価償却の償却超過額の計算パターンが変わってきたり、少しずつ傾向が変わってきている印象です。
2021年9月に出題された問題の他にも、2020年9月の問題では受取配当金の益金不算入額が出題されています。
応用編の問題を解く場合は計算過程の記載が不要な問題でも必ずノートに体裁を揃えて書くようにしています。
何回も同じような問題を同じような体裁に揃えて記載することで視覚や体で覚えることもでき、計算ミスを防ぐこともできます。それに丁寧に計算過程を書くことで少しでも部分点のアピールになればとも思います。
私が実際に使っていた用紙です。
画像をクリックすると拡大します。 注)間違っている箇所もあります(赤字)
まとめ
略式別表四の計算問題は計算式自体は難しくありませんが、問題文が長く読んでいる途中で見落としてしまい計算ミスする場合や、千円単位で記載されている箇所と円単位で記載されている箇所があるのでうっかり桁数を間違えて計算してしまうことがあります。
落ち着いて問題文を読むことと計算単位を円単位にするなど統一しましょう。
FP1級試験では「どっちだったかなぁ」と迷う場面が多々あります。何度も繰り返し問題を解き色々なパターンに対応できるようにしましょう。
最後まで諦めずに実力を発揮できるように頑張りましょう!
ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、FP1級技能士試験のご参考になれば幸いです。