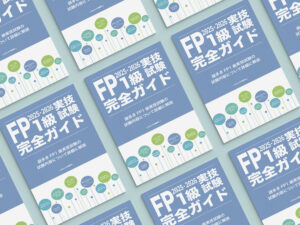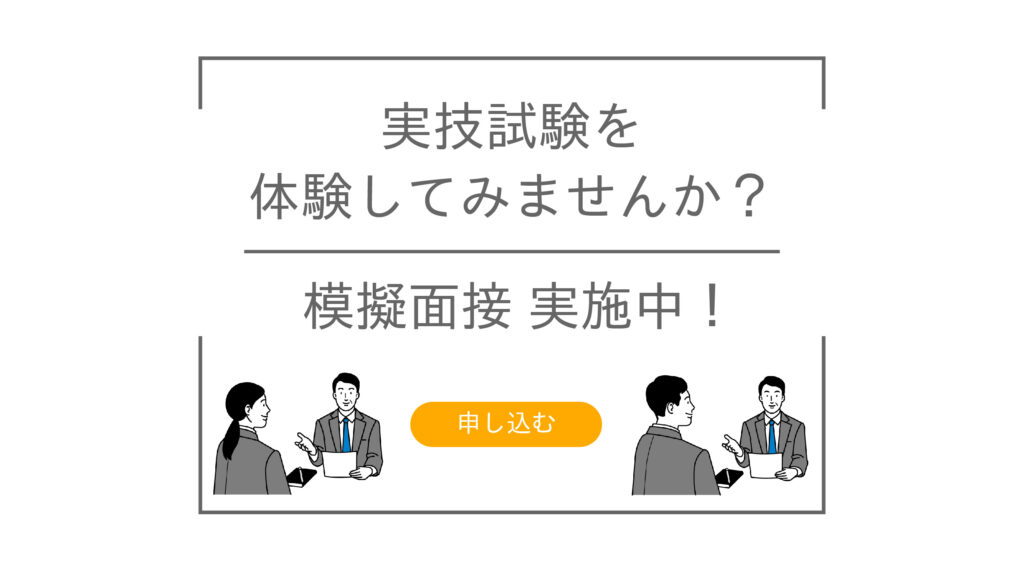2025年度 第1回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2025年6月14日)過去問解説
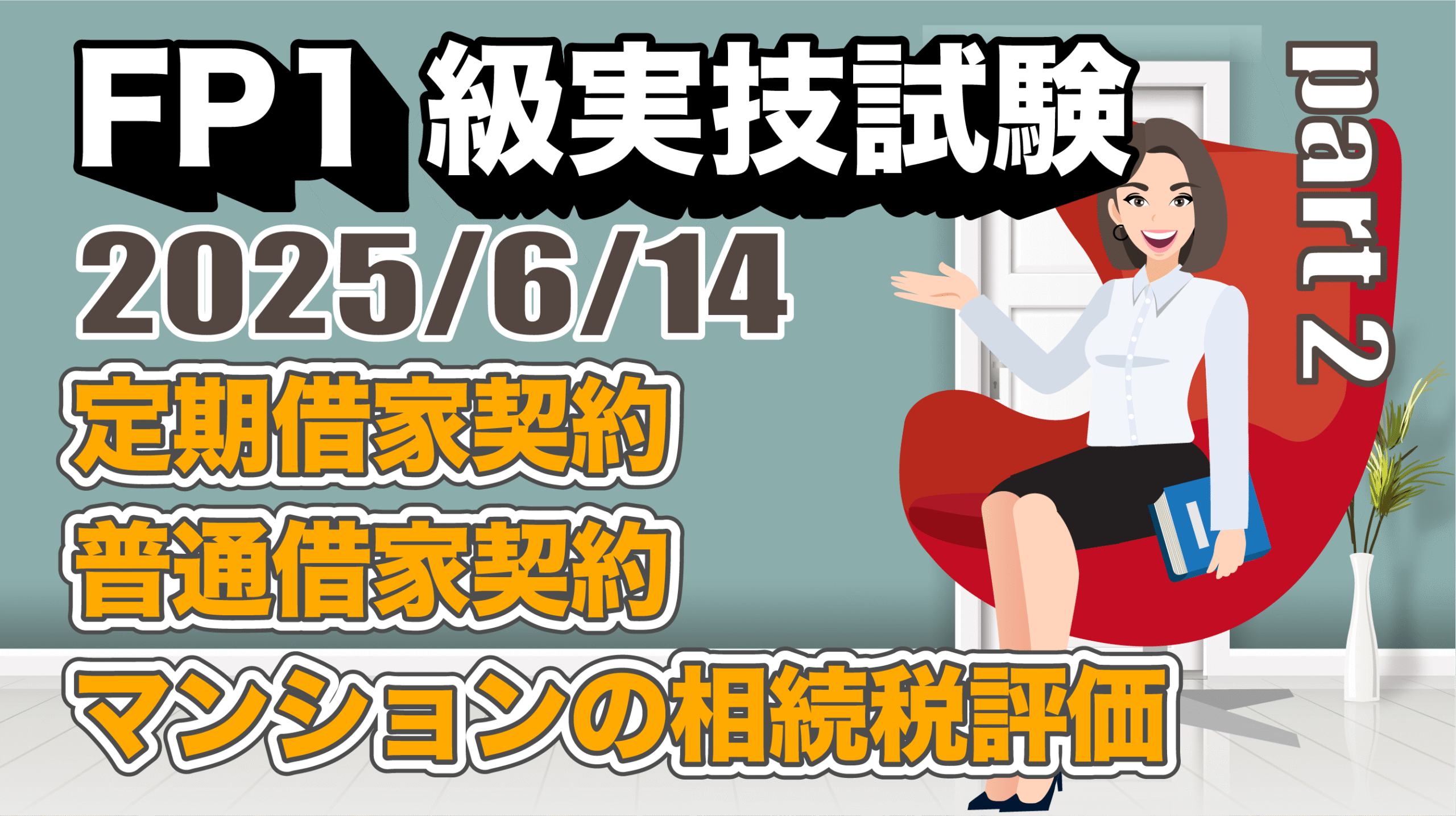
公開日 2025年7月4日 最終更新日 2025年7月9日
合格率1割の難関試験、FP1級学科試験。しかし、学科試験を合格しただけではFP1級技能士の称号は与えられません。
FP1級技能士としての資質が審査される。FP1級実技試験が待っています。
実技試験は学科試験と違い合格率8割以上です。だからといって油断していると足をすくわれます。
合格率1割の難関試験突破者が2割も落ちているんですよ。
1級学科の勉強を始める時に、2級や3級の問題集やテキストは本屋さんにたくさん置いてあるのに1級の本はほとんど置いてなく注文して購入した方も多いのではないでしょうか。
FP1級実技試験は学科試験以上に情報量が少なく、テキストも「きんざいの実技試験対策問題集」ほぼ一択です。
そんな、謎多きFP1級実技試験の過去問を解説します。
試験当日の標準的なスケジュールは以下の通りです。
- 控室で待機(待機中は紙媒体の参考書等は見ることができます。電子機器は使えません)
- 設例を読む机に移動(約15分間設例を読みます。設例にメモやマーカで印をつけます)
- 面接試験室へ移動(心の準備ができたらノックして入室。約12分の口頭試問試験が始まります)
- 面接終了後、控室へ移動(次の試験まで待機)
設例を読むところから試験は始まっています。設例を読み理解することもトレーニングだと思って、タイマーを15分間セットしてメモをとりながら読んでみてください。
それでは、設例をお読みください。
2025年度 第1回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2025年6月14日)
●設 例●
Aさん(45歳)は、専業主婦の妻Bさん(41歳)、長男Cさん(7歳)および長女Dさん(3歳)との4人で地方中核都市のX市内にある賃貸マンションで暮らしている。現在の住まいは2LDKで、長男Cさんが小学生になったため、そろそろ引っ越したい気持ちはあるが、預金は夫婦合わせて1,000万円程度であり、マイホームを取得するには足りないと考えている。これから教育費もかかるので、当分の間は今の賃貸マンションに住み続けざるを得ないと考えている。Aさんの父Eさん(86歳)は、数年前に妻(Aさんの母)を亡くし、現在はAさんの兄Fさん(50歳)家族と同居している。
先日、父Eさんの自宅を訪問した際、父Eさん・兄Fさんと将来の相続やライフプランについて話し合う機会があり、その際に、Aさんは父Eさんに「マイホームはほしいが資金が足りないので、当面は賃貸マンションに住む」という話をした。その話を聞き、父Eさんは、以前、知人からアドバイスされたことがあるとして、Aさんに次のような提案をしてきた。なお、父Eさんは、意思能力も十分で売買契約等の内容も自分で判断することができる。
【父Eさんの提案内容】
兄Fさんは、同居している父Eさんの自宅の土地建物(相続税評価額3,000万円)を相続する。
父Eさんの金融資産9,000万円のうち、3,000万円は預金のままとする。
残りの6,000万円で、父Eさんがマンション(1戸)を購入し、父Eさんが亡くなるまでの生活費や自宅の修繕費等に充てるため、定期借家として賃貸し家賃収入を得る。マンションは、将来Aさんが相続する。
父Eさんの提案に対してAさんは大変ありがたいと思ったが、定期借家などわからない点がいくつかあり、被相続人が相続発生直前に節税対策を目的として購入した不動産について追徴課税が行われたというニュースを聞いたこともあることから、FPであるあなたに相談することにした。
(FPへの質問事項)
Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか。以下の①および②に整理して説明してください。
①Aさんから直接聞いて確認する情報
②FPであるあなた自身が調べて確認する情報父Eさんが、購入したマンションを普通借家ではなく定期借家として賃貸するメリットを教えてください。また、次の時点における定期借家契約と普通借家契約の違いを教えてください。
①契約締結時
②賃借人からの中途解約時
③契約満了時「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)による居住用マンションの相続税評価額の評価方法について教えてください。
仮に、父Eさんがマンションを定期借家として賃貸借契約を締結した2年後に亡くなり、Aさんがマンションを財産評価基本通達と「居住用の区分所有財産の評価について」により評価して相続した場合、課税庁側から財産評価基本通達の総則6項により、評価が見直される可能性はありますか。
【財産評価基本通達とその適用基準】
第1章 総則
(この通達の定めにより難い場合の評価)6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
適用基準①
評価通達に定められた評価方法以外に、他の合理的な評価方法が存在するか
適用基準②
評価通達に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しいかい離が存在するか
適用基準③
課税価格に算入される財産の価額が、客観的交換価値としての時価を上回らないとしても、評価通達の定めによって評価した価額と異なる価額とすることについて合理的な理由があるか
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級実技試験(資産相談業務)2025年6月 参考:技能検定試験問題の使用について
(注)設例に関し、詳細な計算を行う必要はない。
実技試験は口頭試問形式で行われるため模範解答は公表されていません。そのため、審査員の質問や受験者の回答はあくまで個人の見解です。試験問題から予想して質問や回答を掲載していますが、このような質問がない場合や回答している内容が正解とは限りません。
不適切な回答や、より良い回答などございましたらコメント欄、またはX(Twitter)でお知らせください。
○○と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか?
①Aさんから直接聞いて確認する情報は、どのようなことですか?
①Aさんから直接聞いて確認する情報は、
現在の家賃や購入希望のマイホームの詳細。
収入や資産状況。
将来のライフプラン。
父Eさんが購入予定のマンションの詳細。
賃貸マンション経営の経験があるかどうかを確認します。
②FPであるあなた自身が調べて確認する情報は、どのようなことですか?
②FP自身が調べて確認する情報は、
⑴現地確認として、父Eさんが購入を予定しているマンションの(外観、近隣状況、住人)
土地・道路や交通量などの物理的状況を、実際に現地で確認すること。
⑵権利関係として
法務局で登記事項証明書や公図を請求し、権利状況等を確認すること。
⑶法令上の制限として
自治体の都市計画課等で、用途地域・都市計画等を確認し、今後の開発予定や周辺環境の変化などを把握すること。
⑷市場調査として
父Eさんが購入を予定しているマンション周辺の取引事例を、地元の不動産業者等で確認します。
父Eさんが、購入したマンションを普通借家ではなく定期借家として賃貸するメリットを教えてください。
定期借家として賃貸するメリットは、更新がないため必ず退去してもらえることや、短期間でも貸し出せることなどです。
契約締結時点における定期借家契約と普通借家契約の違いを教えてください。
普通借家契約を締結するには口頭でも可能ですが、定期借家契約の場合は、公正証書などの書面によって契約することが必要です。
また、貸主は、契約書とは別に、契約の更新はなく、期間の満了とともに契約終了することを書面としてあらかじめ交付して、借主に説明する義務があります。
この説明を怠ったときは、定期借家契約としての効力がなくなり、普通借家契約になります。
賃借人からの中途解約時点における定期借家契約と普通借家契約の違いを教えてください。
定期借家契約では、途中で解約をすることができないのが原則です。
賃借人からの中途解約は、床面積が200平方メートル未満の住居用の建物に限りますが、転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない正当事由があり、賃借人が該当する賃貸物件を生活の拠点として使用し続けることが困難となった場合は、中途解約の申し入れが可能となります。
普通借家契約は一般的に中途解約に関する条項が記載されており、賃借人からの中途解約はその条項の範囲内で可能です。
契約満了時点における定期借家契約と普通借家契約の違いを教えてください。
定期借家契約は原則として契約の更新はできないので、契約期間終了により賃借人は退去しなければなりません。
ただし、貸主と賃借人の双方が合意すれば、期間満了後の再契約は可能です。
普通借家契約では、契約期間が定められていたとしても賃借人が更新したいと申し出れば更新することが可能です。
正当な事由がない限り、貸主は契約更新を拒絶できません。
「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)による居住用マンションの相続税評価額の評価方法について教えてください。
居住用マンションの相続税評価方法は、相続税評価額に市場価格を反映する指標として区分所有補正率が導入されました。
具体的には、マンションの評価額と市場価格の乖離度を計算するために、築年数、総階数、部屋の所在地、敷地持分狭小度の4要素に基づいた評価乖離率を算出します。
そして、評価乖離率に基づく評価水準に応じて、現行の相続税評価額に区分所有補正率を掛けることで相続税評価額を算定します。
居住用マンションの相続税評価方法の対象となるのは、全てのマンションが対象ですか?
居住用マンションの相続税評価方法の対象は、タワーマンションに限らず、区分所有不動産で居住用部分があるものが対象です。
ただし、2階建て以下の低層マンションや二世帯住宅。
区分建物の登記がされていないもの。
事業用のテナント物件、1棟を所有している賃貸マンションなどは対象外です。
居住用マンションの相続税評価方法によって、どのような影響がありますか?
居住用マンションの相続税評価方法によって、従来の相続税評価額が市場価格を大きく下回る場合には、相続税評価額が市場価格の6割相当額まで引き上げられることになります。
逆に、従来の相続税評価額が市場価格を上回る場合には、相続税評価額が市場価格まで引き下げられることになります。
仮に、父Eさんがマンションを定期借家として賃貸借契約を締結した2年後に亡くなり、Aさんがマンションを財産評価基本通達と「居住用の区分所有財産の評価について」により評価して相続した場合、課税庁側から財産評価基本通達の総則6項により、評価が見直される可能性はありますか。
評価が見直される可能性はないと思います。
財産評価基本通達の総則6項について教えてください。
財産評価基本通達の総則6項とは、国税庁が公表する財産評価基本通達の規定の一つです。
財産の種類ごとに評価方法を定めていますが、この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる場合は、購入価額や不動産鑑定評価額などで評価されることがあり得るというルールです。
どのような場合に、著しく不適当と認められ評価が見直される可能性がありますか。
マンションの購入が税負担の軽減が目的であったり、相続開始直前や、多額の借入による購入の場合や、相続開始後すぐに売却したり、相続税の軽減以外に理由がない場合など、実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、評価が見直される可能性があります。
父Eさんがマンションを購入する目的は、父Eさんが亡くなるまでの生活費や自宅の修繕費等に充てるための家賃収入を得ることが目的です。
また、購入資金も借入金ではなく、金融資産で購入する予定なので評価が見直される可能性はないと思います。
FP業務では、色々な専門職業家と連携することもあると思いますが、
今回のケースで関与する、専門職業家には、どのような方々がいますか?
不動産の取引に関する、課税上の具体的な税務相談は、税理士に、
売買契約等における、宅地建物取引業法に規定する業務については、宅地建物取引士に、
土地の所有権移転登記については、司法書士に、
正確な測量と境界の明示、登記については土地家屋調査士に、
測量に基づく適正な不動産価格の算定は不動産鑑定士と連携します。
質問は以上です。お疲れさまでした。
ありがとうございました。失礼いたします。
今回の設例は、定期借家契約、普通借家契約、居住用マンションの相続税評価に関する設例でした。
実際に受験した方からは、判例の質問があったということでした。
財産評価基本通達6項(総則6項)に関する判例は、相続税における財産の評価方法が、評価通達の規定通りに行われるべきか、それとも実際の取引価格や鑑定評価額を考慮すべきかが争われたものです。
最高裁判決(令和4年4月19日):
相続税の申告において、相続開始直前に不動産を取得し、相続税の負担を減らす目的で行われた取引であると認定され、路線価による評価ではなく、不動産鑑定評価額が適用され、追徴課税が課された事例です。
相続税対策のために評価額の低い財産を取得した場合などに、総則6項を適用して時価での評価が認められるかが焦点となります。
相続税対策を行う際には、評価通達による評価だけでなく、実際の取引価格や鑑定評価額なども考慮し、総合的に判断することが重要です。
FP1級実技試験の難しさは「自分の言葉で相手に伝える」ことだと思います。何度も声に出して読んだり、二人で読み合わせをするなど、お客様に説明するように話してみるのも効果的です。
最後まで諦めずに、FP1級学科試験合格者としての実力を発揮できるように頑張りましょう!
ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、FP1級技能士試験のご参考になれば幸いです。