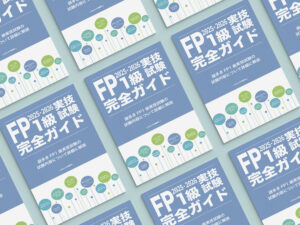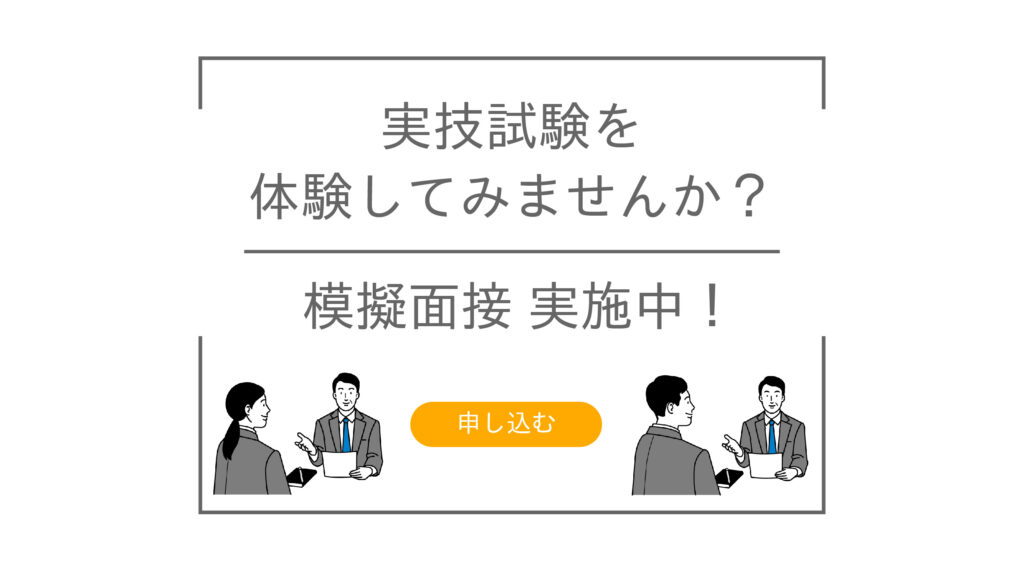【2023年5月試験対策】FP1級試験の出題数ランキング 〜金融資産運用〜
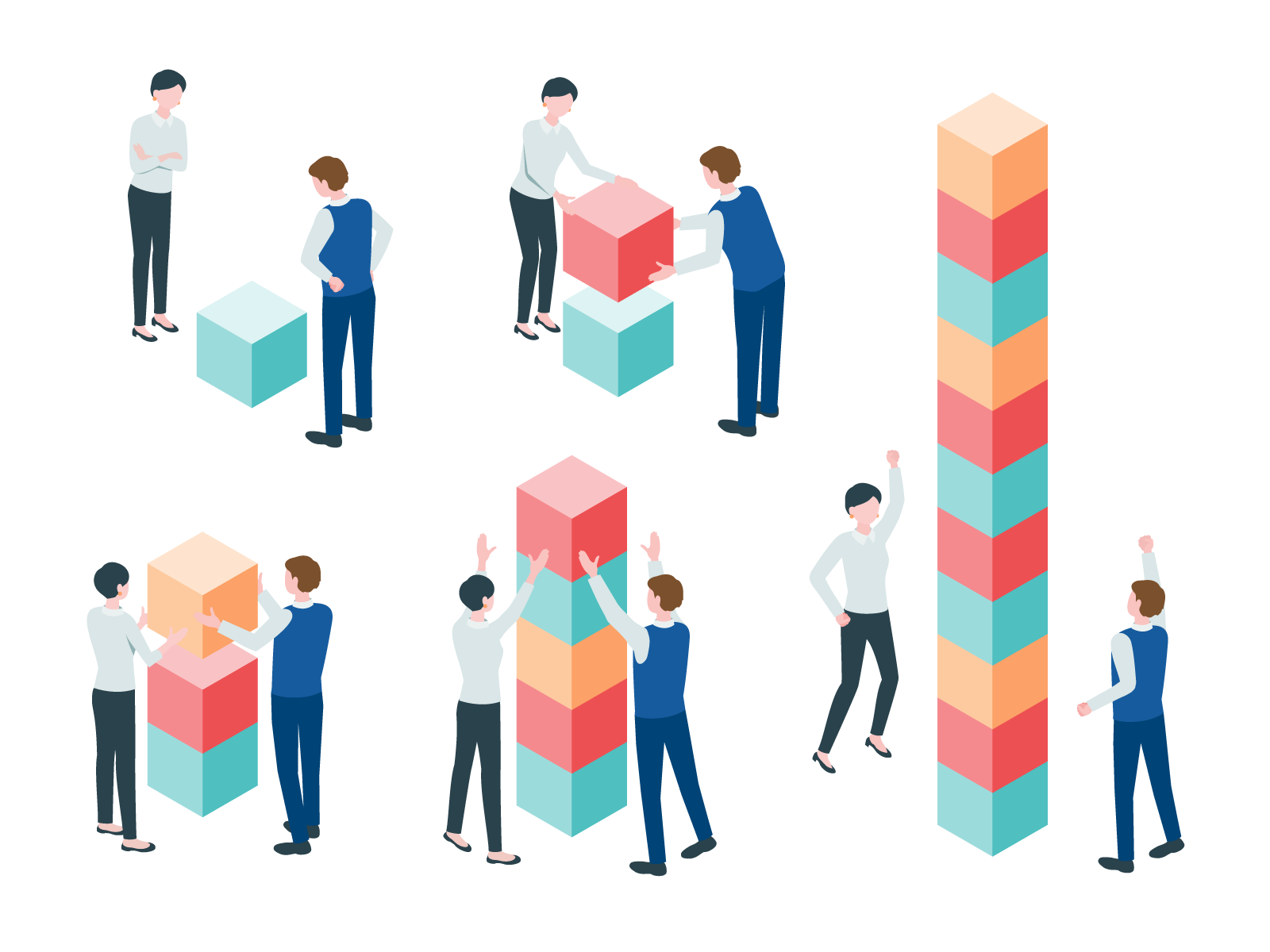
公開日 2023年3月26日 最終更新日 2023年4月16日
FP1級試験の過去問を、何度も繰り返しといていると、「久しぶり!」「会いたかったよ!」「また、おまえかっ!」というように、さまざまな問題との出会いがあります。
旬な話題や制度改正の問題など、一期一会の問題もありますが、何度も繰り返し出題される「常連問題」「ご無沙汰問題」もあります。
過去問題を繰り返し解く!
FP試験に限らず、資格試験対策に有効な勉強方法の一つです。
出題範囲が無限大のFP1級試験でも常連問題があり、常連問題を確実に正解することが大切です。
過去3年間(2020年1月から2023年1月試験までの9回分)の出題問題ランキングを分野別に調べてみました。
2020年1月〜2023年1月までの出題問題一覧
金融資産運用の、2023年1月から過去9回分の試験問題を見てみましょう。
この表では、計算問題を赤文字、それ以外の問題は黒文字で記載しています。
|
2020年1月 |
2020年9月 |
2021年1月 |
2021年5月 |
2021年9月 |
2022年1月 |
2022年5月 |
2022年9月 |
2023年1月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
問16 |
投資信託(種類) |
経済指標 |
経済指標 |
金融政策(時事問題) |
経済指標 |
経済指標(米国) |
景気動向指数 |
日銀とFRBの金融政策 |
金投資 |
|
問17 |
シャープレシオ(計算) |
後見制度支援預金(概要) |
金投資(概要) |
信託商品(概要) |
投資信託(運用スタイル) |
各種信託商品 |
金投資 |
投資信託の費用 |
投資信託のディスクロージャー |
|
問18 |
地方債(種類) |
投資信託(交付書類) |
個人向け国債(概要) |
目論見書(説明) |
割引債券の単価と利付債券の最終利回り(計算) |
ETF(概要) |
投資信託(商品性) |
債券のリスク指標 |
配当予想(配当割引モデル)(計算) |
|
問19 |
株価指標 |
他社株転換可能債(EB債の概要 |
株価指標 |
割引債券・利付債券の最終利回り(計算) |
信用取引(取引例) |
各種債券の商品性 |
固定利付債の利回り(単利)(計算) |
市場区分と株価指数 |
外貨建商品 |
|
問20 |
サスティナブル成長率(計算) |
割引債券・利付債券の最終利回り(計算) |
テクニカル分析(種類・概要) |
株価指標(海外) |
株価指標(海外) |
サスティナブル成長率(計算) |
予想配当に対する期待収益率(計算) |
信用取引 |
ポートフォリオの時間加重収益率(計算) |
|
問21 |
オプション取引(概要) |
信用取引(概要) |
サスティナブル成長率(計算) |
信用取引(概要) |
外貨建預金の利回り(計算) |
日経225先物取引 |
外貨預金の利回り(計算) |
ポートフォリオの標準偏差(計算) |
デリバティブ(リスクヘッジ) |
|
問22 |
行動ファイナンス |
時間加重収益率(厳密法) |
オプション取引(概要) |
デリバティブ取引(リスクヘッジ) |
相関係数(計算) |
①シャープレシオ ②トレイナーレシオ(計算) |
オプション取引のリスクヘッジ |
ポートフォリオ理論 |
特定口座 |
|
問23 |
外貨建金融商品(課税関係) |
株式の配当・譲渡(所得税) |
NISA(概要) |
特定口座(概要) |
NISA(概要) |
外貨建金融商品(課税関係) |
収益分配金(計算) |
米国上場株式取引の課税関係 |
個人情報保護法 |
|
問24 |
金融商品取引法(禁止行為) |
個人情報保護法(概要) |
消費者契約法・金融商品取引法 |
預金保険制度(概要) |
預金保険制度(概要) |
消費者契約法(インサイダー取引) |
預金者保護法 |
金融サービスの提供に関する法律 |
行動ファイナンス |
|
問54 |
財務データ(穴埋、計算) |
財務データ(穴埋、計算) |
NISA |
財務データ(穴埋、計算) |
財務データ(穴埋、計算) |
理論株価(穴埋、計算) |
一般NISA口座 |
株式取引 |
総資産経常利益率(計算) |
|
財務データ(流動比率)(計算) |
総資産回転率(計算) |
||||||||
|
問55 |
使用総資本事業利益率(計算) |
損益分岐点比率(計算) |
①自己資本当期純利益率(計算) |
①使用総資本事業利益率(計算) |
①サスティナブル成長率(計算) |
①固定長期適合率(計算) |
財務データ(固定比率)(計算) |
①自己資本当期純利益率(計算) |
PER・PBR(計算) |
|
②インタレストカバレッジレシオ(計算) |
②インタレストカバレッジレシオ(計算) |
②使用総資本事業利益率(計算) |
②インタレストカバレッジレシオ(計算) |
インタレストカバレッジレシオ(計算) |
②使用総資本事業利益率(計算) |
営業利益(計算) |
|||
|
問56 |
①期待収益率(計算) |
米ドル建債券の所有期間利回り(計算) |
①シャープレシオ(計算) |
①株式取引 |
損益分岐点比率(計算) |
上場株式の配当 |
①相関係数(計算) |
投資信託のパフォーマンス |
損益分岐点売上高(計算) |
|
②標準偏差(計算) |
②標準偏差(計算) |
②上場株式の配当の課税関係 |
②シャープレシオ(計算) |
シャープレシオ(計算) インフォメーション・レシオ(計算) |
米ドル建債券の所有期間利回り(計算) |
金融資産運用は他の分野と比べて、計算問題の出題数が多いのが特徴です。
基礎編でも2問〜3問は計算問題が出題されています。
基礎編の場合は、計算過程を記載する必要はなく、答えは四択なので計算が完璧でなくても解答できそうな気がしますが、FP1級試験はそんなに甘くありません。
「間違って計算した答えが選択肢にある」というトラップが仕掛けられています。
受験生が計算間違えすることを見越して問題を作成し、そのトラップに引っかかるなんて作者にとってはたまらないでしょうね。
意地悪なトラップに引っかからないように、計算問題は完璧にマスターしましょう。
応用編のほとんどは計算問題が出題される
金融資産運用の応用編は、穴埋め問題も出題されていますが、内容は計算問題です。
例えば、「X社とY社を自己資本当期純利益で比較すると、X社の値が( ① )%、Y社の値が( ② )%…」といったように、出題されている計算問題も多種多様で、まぎらわしい計算式もあります。
やはり、計算問題を制することが金融資産運用を制すると言えます。
基礎編の出題ランキング
基礎編の出題ランキング
(2020年1月〜2023年1月まで 9回分を集計)
基礎編の出題ランキングを見てみましょう。
基礎編で出題される、金融資産運用の問題は問16から問24までの8問です。
ランキング上位は、投資信託、株価指標、外貨建て商品、経済指標、信用取引です。
ランキング1位の投資信託に関する問題は、投信の種類や交付書類、運用スタイルや商品性、コストなどに関する問題が出題されています。
基礎編の8問の中に、計算問題が1問から多い時で3問出題されており、債券の利回り計算、サスティナブル成長率、シャープレシオなど応用編でも出題される問題が基礎編でも出題されています。
基礎編の戦略
FP1級の学科試験は、基礎編と応用編の合計点数が、200点満点中120点以上で合格できます。
したがって、全ての問題を正解する必要はありません。6割以上で合格です。
2級までは、8割〜9割の正解率で合格した方も多いと思いますが、
1級の場合は、6割から8割の正答率で合格した方が多いのではないでしょうか。
FP1級試験合格を最優先に考えた場合、基礎編と応用編の得点割合や、6分野ごと出題数から勝敗を考えて戦略を練ることも大切です。
金融資産運用の基礎編は6勝2敗を目指す
先ほどもお話ししたように、金融資産運用の基礎編は、8問の中に計算問題が1問から3問出題されます。
まずは、基礎編でも計算問題を確実に正解し、残りの5問から6問での間違いを2問ぐらいに抑えることができれば、基礎編で12点取ることができます。
文章問題に関しては、まったく聞いたこともない、未知の問題との出会いもありますが、金融商品取引法や消費者契約法、個人情報保護法などの法律問題も出題されるので、選択肢をよく読むと明らかにおかしな文章に気づくことができます。
金融資産運用でも、四択を三択か二択に絞ることができるようにテキストにもよく目を通しておきましょう。
私が初めて受験した、2020年1月の試験では、3勝5敗と大きく負け越しましたが、2回目に受験した2020年9月の試験では6勝2敗とリベンジに成功しました。
2回目の試験で間違えた2問は、「他社株転換可能債(EB債)の概要」に関する問題と、「株式の配当、譲渡に係る所得税の取扱い」に関する問題でした。
計算問題をすべて正解できたのが大きかったと思います。
応用編の出題ランキング
応用編の出題ランキング
(2020年1月〜2023年1月まで 9回分を集計)
応用編の出題ランキングを見てみましょう。
応用編で出題される金融資産運用の問題は、計算問題がほとんどです。
穴埋め問題も出題されますが、結局は計算して解答する問題です。
語句を解答する穴埋め問題を作りにくい分野なのか、制度の内容など、語句を解答する問題は「NISA」や「株式取引」「配当」に関する問題です。
今後は、NISA制度改正なども予定されていますので、改正に関する問題の出題が増えるかもしれませんね。
応用編の戦略
FP1級試験では、基礎編よりも応用編で点数を稼ぐというのが王道です。
合格した方のほとんどは、基礎編よりも応用編の点数の方が高いと思います。
私の場合も、基礎編70点、応用編76点の合計146点でした。
出題範囲が無限大の基礎編よりも、ある程度を絞ることができる応用編で取りこぼすことはできません。
財務データの計算問題も完璧にマスターし、穴埋め問題は全問正解を目指す
計算問題の多くは、財務データに関する問題です。
穴埋め問題の形式でも出題されるので、問題数は多く出題されます。
まずは財務データに関する計算を完璧にマスターしておくことが大切です。
財務データに関する問題の中でも、「使用総資本事業利益率」や「インタレストカバレッジレシオ」は、計算過程を示す問題として出題されることも多く、配点が高く設定されていたり、部分点の獲得チャンスもあるため取りこぼしは許されません。
私の場合、穴埋め問題はすべて正解できたのですが、計算過程を示す問題を2問とも間違えてしまい、大きく点数をロスしてしまいました。(損益分岐点比率と米ドル建て債券の所有期間利回りの問題でした)
過去問で完璧に正解できていても、本番で間違ってしまうのがFP試験の怖さです。
本番では問題用紙の空いているスペースか、下書き欄に計算式を記入することになると思うので、日頃から本番と同じように、限られたスペースでも計算過程を丁寧に書き、解答できるようにしておきましょう。
計算問題を、確実に正解することが重要
金融資産運用は、文章問題はもちろんですが、計算問題をどれだけ多く正解できるかが合否を分ける鍵になります。
計算式も多く、覚えるのも大変ですが、計算式自体はそこまで難しい式ではないので、紙に書いて整理したり、電卓を打つ順番を体に覚え込ませるなどして覚えましょう。
応用編の穴埋め問題で出題される内容は、基礎編ほどの難しい内容が出題されることはなくFP2級の難易度に近い問題です。
ジャンルもほぼ決まっているので、ここでの取りこぼしはもったいないですね。
ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。皆さんのFP1級技能士試験合格を願っています。