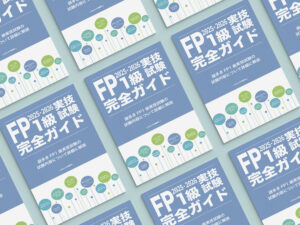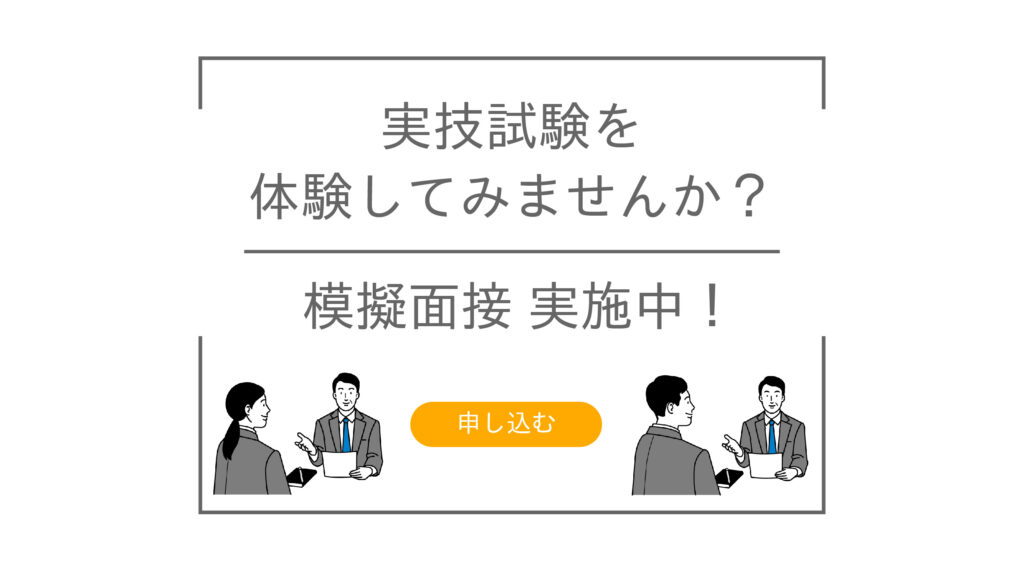2025年度 第1回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 1 (2025年10月4日)過去問解説
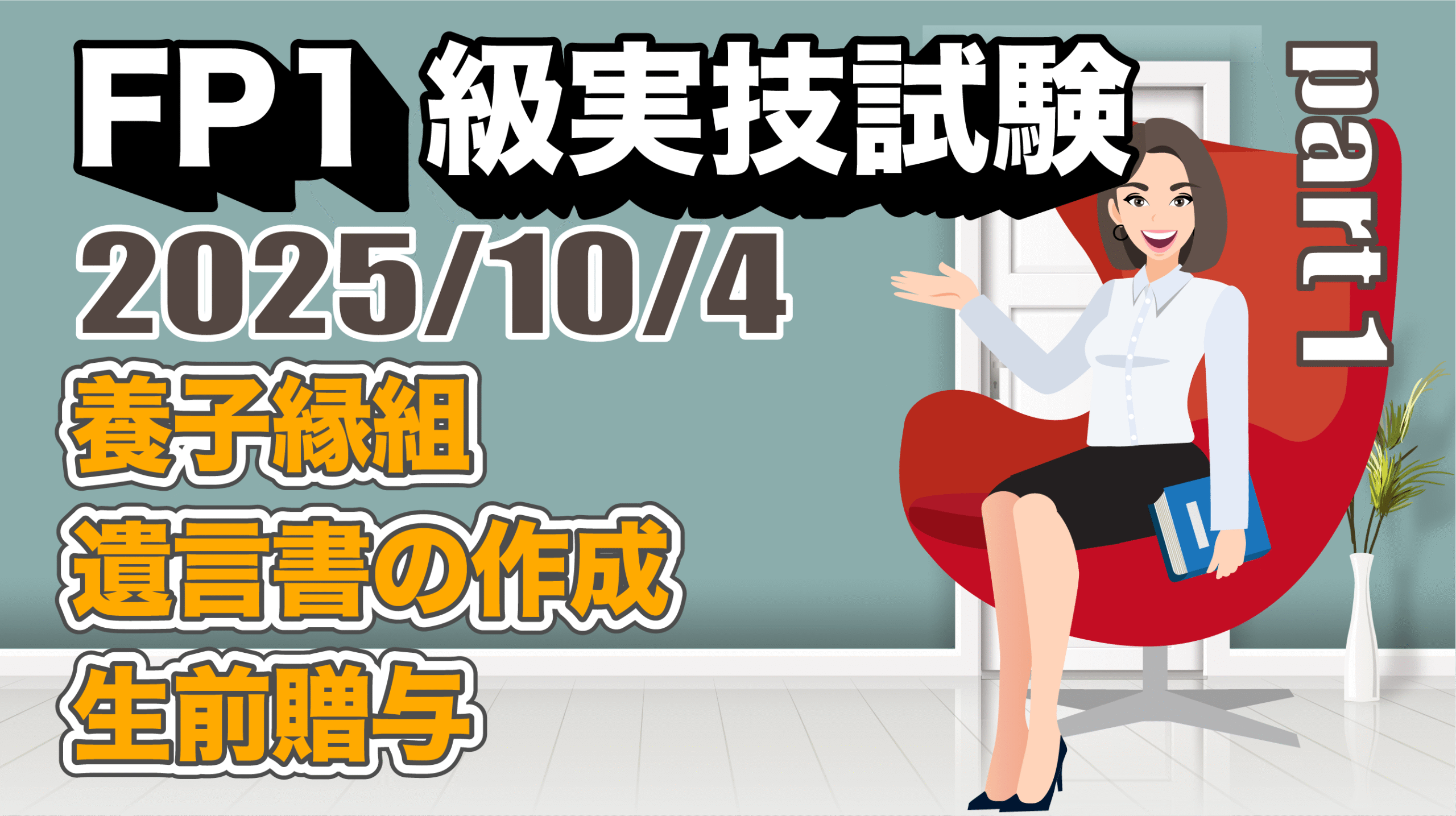
合格率1割の難関試験、FP1級学科試験。しかし、学科試験を合格しただけではFP1級技能士の称号は与えられません。
FP1級技能士としての資質が審査される。FP1級実技試験が待っています。
実技試験は学科試験と違い合格率8割以上です。だからといって油断していると足をすくわれます。
合格率1割の難関試験突破者が2割も落ちているんですよ。
1級学科の勉強を始める時に、2級や3級の問題集やテキストは本屋さんにたくさん置いてあるのに1級の本はほとんど置いてなく注文して購入した方も多いのではないでしょうか。
FP1級実技試験は学科試験以上に情報量が少なく、大きめの書店でもテキストを見かけることは滅多にありません。
そんな、謎多きFP1級実技試験の過去問を解説します。
試験当日の標準的なスケジュールは以下の通りです。
- 控室で待機(待機中は紙媒体の参考書等は見ることができます。電子機器は使えません)
- 設例を読む机に移動(約15分間設例を読みます。設例にメモやマーカで印をつけます)
- 面接試験室へ移動(心の準備ができたらノックして入室。約12分の口頭試問試験が始まります)
- 面接終了後、控室へ移動(次の試験まで待機)
設例を読むところから試験は始まっています。設例を読み理解することもトレーニングだと思って、タイマーを15分間セットしてメモをとりながら読んでみてください。
それでは、設例をお読みください。
2025年度 第1回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 1 (2025年10月4日)
●設 例●
Aさん(70歳)は、個人で不動産賃貸業を営んでおり、賃貸マンションと月極駐車場から年間600万円の収入を得ている。金融資産も潤沢にあることから、生活は安定している。Aさんには離婚歴があり、前妻との間に子Cさん(40歳)がいる。また、18年前に再婚した妻Bさん(62歳)にも離婚歴があり、前夫との間の子であるDさん(38歳)がいる。再婚時にDさんは既に成人し、結婚していたこともあり、AさんはDさんと養子縁組をしていない。Aさんは、自宅を10年前に二世帯住宅(区分所有登記はされていない)に建て替え、現在は妻BさんおよびDさん家族と同居している。なお、AさんとDさん家族は生計を別にしている。
AさんとDさんの関係は良好であり、AさんはDさんの子にも愛情を注いでいる。一方、前妻との間の実子である子Cさんは、妻Bさんとの折り合いが悪く、最近はほとんどAさん宅に顔を見せることはない。
Aさんは最近大病をしたこともあり、そろそろ相続の準備を始め、必要に応じて何らかの対策を講じておきたいと考えている。Aさんは実の娘のように思っているDさんに多くの財産を残したいと考えているが、Dさんには法的な相続権がないことから、どのように財産を相続させればよいかわからない。Dさんも、Aさんや妻Bさんに万一のことがあった場合、自分や家族がこれからも現在の自宅に住み続けることができるのかどうか、不安に思っている。
また、Aさんは、当面の相続対策として、毎年Dさんに110万円の暦年課税による現金の贈与を行うつもりであるが、何か問題がないか知りたいと思っている。
【Aさんの家族構成】
妻Bさん(62歳):専業主婦。自宅でAさんと同居している。
子Cさん(40歳):会社員。夫と2人で賃貸マンションに住んでいる。
Dさん(38歳):専業主婦。夫と子の3人でAさん所有の二世帯住宅に住んでいる。
【Aさんの所有財産の概要】(相続税評価額、土地は小規模宅地等の評価減適用前)
⒈ 現預金 : 6,000万円 ⒉ 有価証券 : 2,000万円 ⒊ 自宅 ①土地(330㎡) : 8,000万円 ②建物(築10年) : 3,000万円 ⒋ 賃貸アパート(一戸) : 3,000万円 (年間賃料収入200万円) ⒌ 月極駐車場(500m²) : 3,000万円 (年間賃料収入400万円) 合計 : 2億5,000万円
※月極駐車場は、アスファルトや砂利を敷いておらず、更地にロープを張っただけのいわゆる青空駐車場である。
※Aさんの相続に係る相続税額は、約4,900万円(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の評価減適用前)と見積もられている。
※Aさんは、契約者(=保険料負担者)・被保険者をAさん、死亡保険金受取人を妻Bさんとする生命保険(死亡保険金1,000万円)に加入している。(注)設例に関し、詳細な計算を行う必要はない。
検討のポイント
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級実技試験(資産相談業務)2025年10月 参考:技能検定試験問題の使用について
●設例の顧客の相談内容および問題点として、どのようなことが考えられるか。
●それらの相談内容および問題点を解決するために、どのような提案・方策が考えられるか。
●それらの方策(解決策)のなかで、何を顧客に提案するか。その理由・留意点は何か。
●FPと職業倫理について、どのようなことが考えられるか。
実技試験は口頭試問形式で行われるため模範解答は公表されていません。そのため、審査員の質問や受験者の回答はあくまで個人の見解です。試験問題から予想して質問や回答を掲載していますが、このような質問がない場合や回答している内容が正解とは限りません。
不適切な回答や、より良い回答などございましたらコメント欄、またはX(Twitter)でお知らせください。
○○と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
設例をじっくり読んだと思いますが、Aさんの相談内容と問題点について項目だけで構いませんので全てあげてください。
相談内容として
- 相続対策を考えていること。
- 法的な相続権がないDさんにどのように財産を相続させればよいか。
-
Aさんや妻Bさんに万一のことがあった場合、Dさんや家族がこれからも現在の自宅に住み続けることができるのかどうか。
-
毎年Dさんに110万円の暦年課税による現金の贈与を行うつもりであるが、何か問題がないか知りたいと思っていることです。
問題点は、
- 相続税が高額になるので相続税の軽減。
- 納税資金の確保。
- 円滑な遺産分割の対策が必要です。
それでは、今あげた問題点を解決するためにどのような提案・方策が考えられますか?
法的な相続権がないDさんに財産を遺す方法は、どのような方法が考えられますか?
法的な相続権がないDさんに財産を遺す方法は、
Dさんと養子縁組をする方法。
遺言書を作成してDさんに遺贈する方法。
Dさんに生前贈与をする方法の3つがあります。
養子縁組をする方法について説明してください。
養子縁組とは、血縁関係にない者同士の間に、法律上の親子関係を作る制度のことです。
養子縁組を結ぶと、Dさんとの間で法律上の親子関係が成立します。
養子縁組を結び法律上の親子関係が成立すれば、養子になったDさんも法定相続人となります。
そのためAさんが亡くなったときは、血縁関係のあるCさん同様、Dさんにも法的な相続権が認められます。
普通養子縁組の主な要件を教えてください。
養親は20歳以上であること。
養子縁組をするには、養親本人と養子本人の合意が必要なこと。養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人が、養子本人に代わって養子縁組の合意をします。
養親又は養子に配偶者がいる場合には、原則として、その配偶者の同意が必要です。
遺言書を作成してDさんに遺贈する方法について説明してください。
遺言書を作成するとは、財産をDさんに遺贈するという内容の遺言を残しておく方法です。
注意する点はありますか?
作成する際は、Cさんの遺留分を侵害しないように注意が必要です。
遺言書でDさんに多くの財産を遺そうとして遺留分を侵害すると、Cさんから遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
また、作成方法のミスや遺留分への配慮不足から、後でトラブルになる可能性があるため、公正証書遺言の作成や専門家へ相談するようにアドバイスします。
遺贈によって相続権のないDさんに対し財産を引き継いだ場合、相続税が2割加算されます。
また、場合によっては債務や連帯保証人の立場といったマイナスの財産も引き継がなければならない点や、法定相続人以外に不動産を引き継ぐ場合、不動産取得税がかかる点には注意が必要です。
Dさんに生前贈与をする方法を教えてください。
Aさんの生前に双方で贈与契約を結び、財産を贈与する方法です。
生前贈与をするとAさんが亡くなる前に、法定相続人ではないDさんにも財産を引き継ぐことができます。
毎年Dさんに110万円の暦年課税による現金の贈与を行うつもりですが、何か問題はありませんか?
贈与税には基礎控除があるため、年間110万円までであれば無税で贈与できます。しかし、定期贈与とみなされてしまうと贈与税の対象になるため注意が必要です。
定期贈与とみなされず生前贈与を行うためには、どのような方法がありますか?
贈与をする度に贈与契約書を作成しておくこと。
基礎控除を少し超える額の贈与を行い、贈与税の申告を行うこと。
毎年、同じ時期に同じ金額を贈与するのではなく、時期や金額を変えて行う方法があります。
Aさんや妻Bさんに万一のことがあった場合、Dさんや家族がこれからも現在の自宅に住み続けることはできますか?
Aさんが先に亡くなり、妻Bさんが自宅の所有権を相続した場合、Bさんが将来亡くなると、Dさんに自宅の所有権は相続され、現在の自宅に住み続けることはできます。
ただし、現状のままだと、妻Bさんが自宅の所有権をスムーズに相続できるとは限らないので、Dさんとの養子縁組や遺言書を作成することをアドバイスします。
Aさんは、契約者(=保険料負担者)・被保険者をAさん、死亡保険金受取人を妻Bさんとする生命保険(死亡保険金1,000万円)に加入しています。
妻Bさんが先に亡くなった場合は受取人をDさんにすることは可能でしょうか?
Dさんを受取人にするには、養子縁組をすることが確実な方法ですが、養子縁組をしていない場合でも、保険会社によっては認められることがあります。
また、養子縁組をせずにDさんが保険金を受け取る場合、相続税の非課税枠が適用されないなどの相続税上の注意点があります。
最後に、FPが守るべき職業倫理を6つあげてください。
顧客利益の優先、守秘義務の遵守、顧客に対する説明義務、インフォームドコンセント、コンプライアンスの徹底、FP自身の能力の啓発です。
どれもFPにとっては大事なことだと思いますが、今回のケースでは特にどれを重視しますか?
今回のケースでは、インフォームドコンセントを重視します。
Aさんと妻Bさんは再婚同士でそれぞれに子供もいます。
しかし、前妻との間の実子である子Cさんは、妻Bさんとの折り合いが悪く、最近はほとんどAさん宅に顔を見せることはないということです。
相続手続きが複雑になることも考えられるので、一つ一つ制度の内容や適用効果を説明することだけでなく、ご家族と一緒に理解状況を確認しながら、寄り添ったわかりやすく丁寧な説明を行い、必ず同意を得て提案することを重視します。
質問は以上です。お疲れさまでした。
ありがとうございました。失礼いたします。
今回は、養子縁組、遺言書の作成、生前贈与に関する設例でした。
遺産分割に関する内容でしたが、一般的な相続手続きや必要書類だけでなく、Aさんは、個人で不動産賃貸業を営んでおり複数の不動産を所有しているので、不動産に関する相続もチェックしておきましょう!
FP1級実技試験の難しさは「自分の言葉で相手に伝える」ことだと思います。何度も声に出して読んだり、二人で読み合わせをするなど、お客様に説明するように話してみるのも効果的です。
最後まで諦めずに、FP1級学科試験合格者としての実力を発揮できるように頑張りましょう!
ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Xにてお知らせください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、FP1級技能士試験のご参考になれば幸いです。