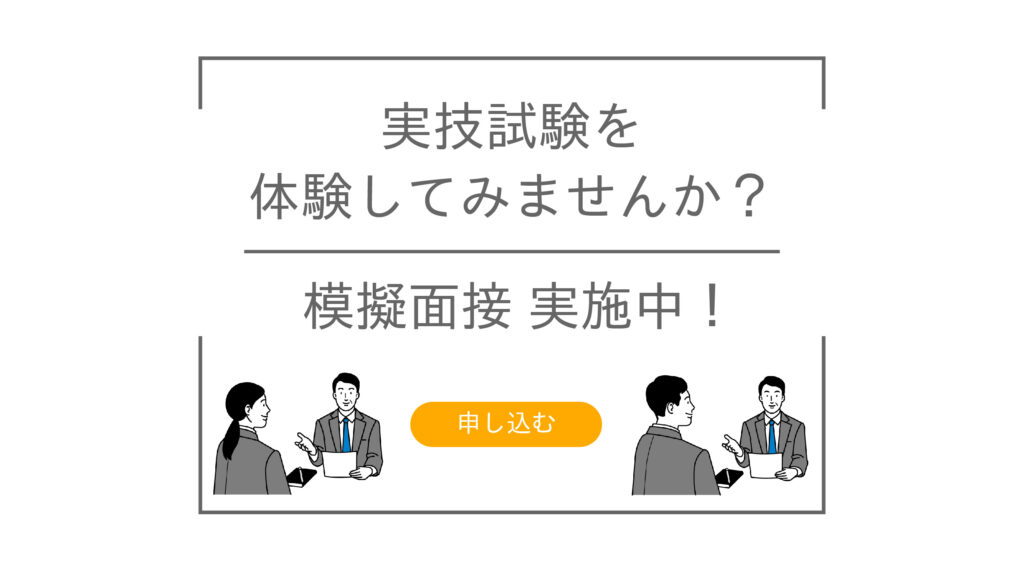2025年度 第1回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2025年10月5日)過去問解説
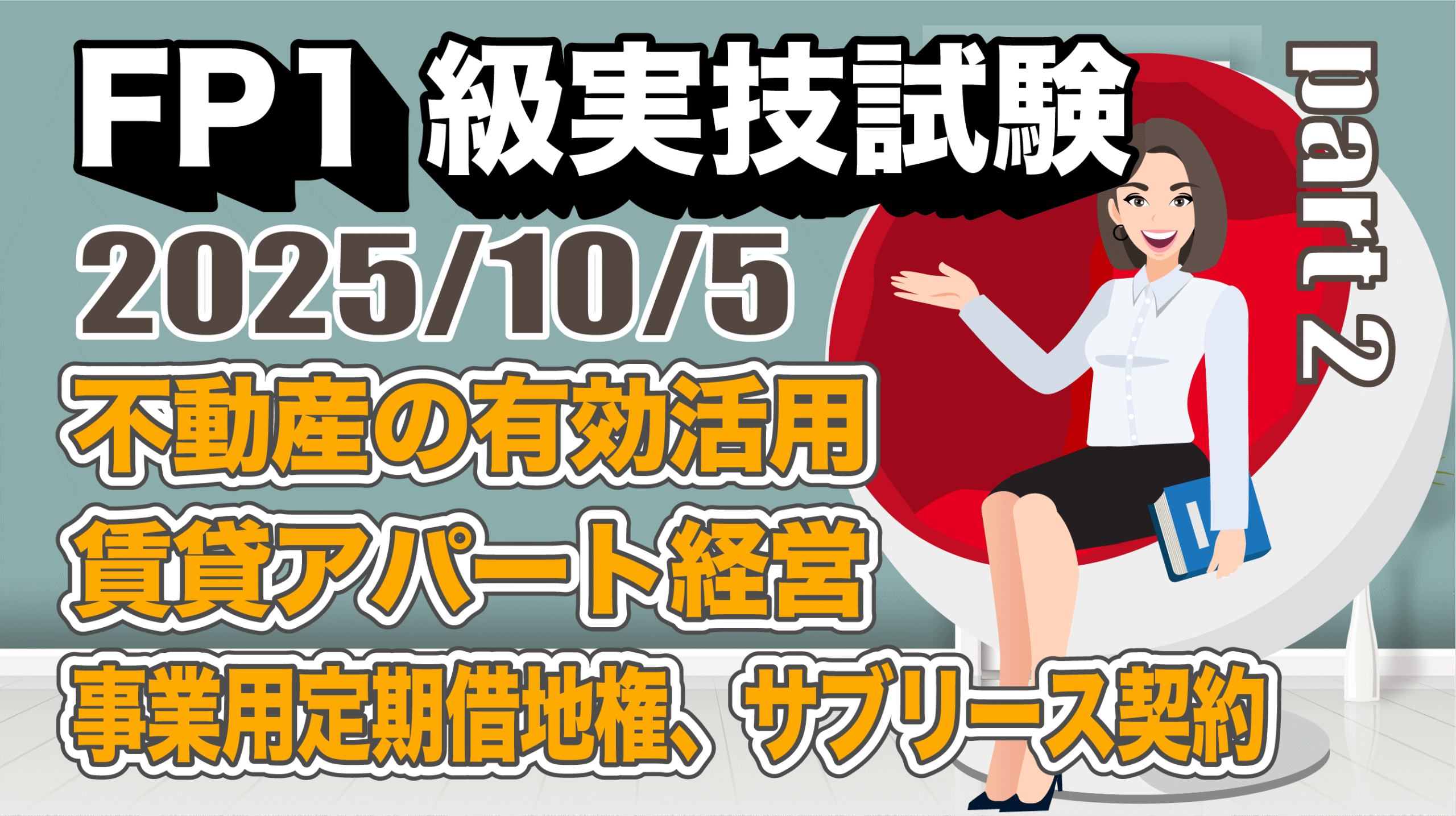
合格率1割の難関試験、FP1級学科試験。しかし、学科試験を合格しただけではFP1級技能士の称号は与えられません。
FP1級技能士としての資質が審査される。FP1級実技試験が待っています。
実技試験は学科試験と違い合格率8割以上です。だからといって油断していると足をすくわれます。
合格率1割の難関試験突破者が2割も落ちているんですよ。
1級学科の勉強を始める時に、2級や3級の問題集やテキストは本屋さんにたくさん置いてあるのに1級の本はほとんど置いてなく注文して購入した方も多いのではないでしょうか。
FP1級実技試験は学科試験以上に情報量が少なく、テキストも「きんざいの実技試験対策問題集」ほぼ一択です。
そんな、謎多きFP1級実技試験の過去問を解説します。
試験当日の標準的なスケジュールは以下の通りです。
- 控室で待機(待機中は紙媒体の参考書等は見ることができます。電子機器は使えません)
- 設例を読む机に移動(約15分間設例を読みます。設例にメモやマーカで印をつけます)
- 面接試験室へ移動(心の準備ができたらノックして入室。約12分の口頭試問試験が始まります)
- 面接終了後、控室へ移動(次の試験まで待機)
設例を読むところから試験は始まっています。設例を読み理解することもトレーニングだと思って、タイマーを15分間セットしてメモをとりながら読んでみてください。
それでは、設例をお読みください。
2025年度 第1回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2025年10月5日)
●設 例●
Aさん(66歳)は、昨年T市の小学校を退職し、同市内の自宅で妻Bさん(63歳)と暮らしている。1人息子の長男Cさん(34歳)は、T市内で公務員として働いており、同市内の賃貸マンションで1人暮らしをしている。退職前のAさんの年収は約550万円であったが、現在は共済組合からの年金収入(年額250万円)と預貯金を取り崩して生活している。Aさんの現在の預貯金残高は1,800万円程度であり、今後の生活を考えると、夫婦の年金収入だけでは心許ないと感じている。退職金については、大部分を自宅に係る住宅ローンの返済やリフォーム費用等に使ったため、手元にはほとんど残っていない。
Aさんは父親から引き継いだT市内の甲土地(400㎡、JR線のターミナル・T駅から1駅であるS駅から徒歩5分)をアスファルト敷きの月極駐車場として利用しており、年間160万円程度の収入を得ているが、固定資産税・都市計画税を毎年100万円程度支払っており、その収益性は高くない。なお、甲土地は先祖代々の土地であり、売却することは考えていない。
Aさんは、今後も退職前と同程度の収入を維持し、加えて将来長男Cさんに迷惑がかからないように、医療費や介護費用への備えとして一定程度蓄えができるよう、甲土地の収益性を高めたいと考えている。
Aさんが、甲土地の有効活用についてメインバンクから紹介された銀行系列の不動産会社であるY社に相談をしたところ、賃貸アパートの建設(右貢の<資料①>参照)の提案を受けた。当地域では、40㎡~45㎡の賃貸住宅が慢性的に不足しているため、賃貸アパートの需要が高いとのことである。
また、地元の不動産会社にも同様の相談をしたところ、担当者を通じて、全国に展開している大手リユースショップのZ社から、事業用定期借地権(右貢の<資料②>参照)の提案を受けた。
Aさんは、Y社とZ社の提案について、どちらがより望ましいのか、またそれをどのように判断すれば良いのかわからず悩んでいる。
このような状況のもと、FPであるあなたに相談があった。
(FPへの質問事項)
Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか。以下の①および②に整理して説明してください。
①Aさんから直接聞いて確認する情報
②FPであるあなた自身が調べて確認する情報不動産の有効活用の方法を決定するために、一般的にどのような事項を検討すべきでしょうか。
Y社とZ社の提案について、あなたであればAさんにどちらの案を勧めますか。その理由とともに教えてください。
本事案に関与する専門職業家にはどのような方々がいますか。
<資料①>Y社からの提案内容
軽量鉄骨造2階建て、延べ面積480㎡、総戸数10戸(専有面積平均45㎡)。
建築費総額1億3,000万円、満室時月額賃料130万円(13万円×10室)。
満室時の経費(固定資産税・都市計画税を含む)は年間約310万円を見込んでいる。
※建築費は全額銀行からの借入れとし、その年間返済額は元金と利息の合計で約580万円である。なお、金融機関からは、融資申込の条件として長男Cさんを連帯保証人とすることを求められている。
サブリースを希望する場合は、当初15年間、満室想定賃料の85%相当額を保証する。それ以後の賃料は、市場賃料を踏まえて協議のうえ決定する。
<資料②>Z社からの提案内容
借地期間30年の事業用定期借地権を契約し、Z社の店舗所有目的で賃貸する。
月額地代は50万円、Z社は、賃貸借期間満了後、建物を解体のうえ、更地で返還する。
固定資産税、都市計画税支払後の年間収入額は約500万円となる見込みである。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級実技試験(資産相談業務)2025年10月 参考:技能検定試験問題の使用について
(注)設例に関し、詳細な計算を行う必要はない。
実技試験は口頭試問形式で行われるため模範解答は公表されていません。そのため、審査員の質問や受験者の回答はあくまで個人の見解です。試験問題から予想して質問や回答を掲載していますが、このような質問がない場合や回答している内容が正解とは限りません。
不適切な回答や、より良い回答などございましたらコメント欄、またはX(Twitter)でお知らせください。
○○と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか?
①Aさんから直接聞いて確認する情報は、どのようなことですか?
①Aさんから直接聞いて確認する情報は、
将来のライフプラン。
資産状況や今後の相続・贈与の予定。
今後の土地活用の目的(安定収入を重視するのか、資産形成・相続対策を重視するのか)
アパート経営を家族も管理する意思・能力があるかを確認します。
②FPであるあなた自身が調べて確認する情報は、どのようなことですか?
②FP自身が調べて確認する情報は、
⑴現地確認として(外観、近隣状況、住人)
土地の形状や高低差・接道状況や交通量、上下水道・ガス・電気などのインフラ整備状況、騒音・日照・治安などの物理的状況を、実際に現地で確認すること。
⑵権利関係として
法務局で登記事項証明書や公図を請求し、土地の権利状況等を確認すること。
⑶法令上の制限として
自治体の都市計画課等で、用途地域・都市計画等を確認し、今後の開発予定や周辺環境の変化などを把握すること。
条例による戸数制限・建物構造などが都市計画上問題ないか。
⑷市場調査として
建設業者やY社の取引事例や財務状況、アフターサポート体制を確認すること。
収支シミュレーションや事業計画の妥当性、建築費の見積もり、空室状況など、
周辺の取引事例を、地元の不動産業者等で確認し、提案は妥当かを確認します。
不動産の有効活用の方法を決定するために、一般的にどのような事項を検討すべきでしょうか?
不動産の有効活用を検討する際には、土地の条件・経済性・法的制約・リスク管理・目的の明確化という5つの観点から整理して考えることが重要です。
まず、土地や建物の現況を確認します。立地、面積、形状、接道、用途地域などの物的条件を把握し、活用の可能性を確認します。
次に、経済性の分析です。活用後の収益や必要な投資額、資金調達方法、税負担などを試算し、採算性・キャッシュフローを検討します。
三つ目は、法的な制約の確認です。都市計画法や建築基準法などの法令上の制限を把握し、建築や用途変更の可否を確認します。
四つ目に、リスクと管理体制の検討です。空室リスク、老朽化リスク、賃貸管理の手間や費用など、運営面のリスクに対応できる体制を整えることが必要です。
最後に、活用の目的を明確にすることです。長期の安定収入を重視するのか、相続税対策や資産の組み換えを目的とするのかによって、最適な方法が異なります。
これらを総合的に検討し、所有者のライフプランや資産全体のバランスに合わせて、有効活用の方針を決定します。
Y社とZ社の提案について、あなたであればAさんにどちらの案を勧めますか?
その理由とともに教えてください。
Z社の提案を勧めます。
どうしてですか?
Z社の提案を勧める理由は、Y社の賃貸アパート経営と比較すると、事業用定期借地権は安定した収入を確保しつつ、リスクや管理負担を大幅に抑えられるからです。
賃貸アパート経営は、建物を所有することで家賃収入や相続税の評価減といったメリットがあります。
一方で、空室リスク・修繕費・金利上昇リスク・入居者対応など、経営上の負担が大きくなり、借入を伴う場合は返済負担が長期化するため、収益が安定するまでのリスクがあります。
事業用定期借地権は建物を所有せず、土地を貸すだけで地代収入を得る仕組みのため、初期投資や維持管理の負担がなく、安定的なキャッシュフローを確保できます。
また、契約期間が満了すれば更地が返還されるため、将来の再活用や売却など、資産の自由度も残せます。
賃貸アパート経営のメリットとデメリットを説明してください。
メリットとしては、定期的な家賃収入を得られる安定収益型の資産である点です。
また、建物を建てることで土地が貸家建付地として評価減され、相続税の軽減効果が得られます。
さらに、建物の減価償却によって所得税の節税効果も期待できます。
デメリットとしては、空室や家賃下落といった経営上のリスクがあります。
また、修繕費や管理費などの維持コストが継続的に発生し、借入を利用する場合は金利上昇や返済負担のリスクもあります。
加えて、入居者対応や建物管理など、経営の手間や時間がかかる点も注意が必要です。
事業用定期借地権のメリットとデメリットを説明してください。
メリットとしては、建物を所有しないため、初期投資や維持管理の負担が少なく、安定した地代収入を長期間得られる点です。
地代は契約で定めた金額をもとに継続的に受け取れるため、景気変動や空室リスクの影響を受けにくく、安定的なキャッシュフローを確保できます。
また、建物の修繕や管理は借地人であるZ社の負担となるため、経営の手間やトラブル対応が不要という点も大きな利点です。
さらに、契約期間が満了すれば更地が返還されるため、将来的な土地の自由度を維持できることもメリットです。
デメリットとしては、アパート経営と比較して地代収入が相対的に少なく、相続税評価の圧縮効果も限定的である点が挙げられます。
また、契約期間中は原則として土地を自由に売却・転用できず、途中解約も難しいため、流動性が低下します。
さらに、長期契約のため、将来の地代の見直しが難しい場合もあります。
Y社からは、サブリースも提案されています。
サブリース契約のメリットとデメリットを説明してください。
メリットとしては、空室や滞納があっても、サブリース会社が一括して家賃を保証してくれるため、オーナーは安定した賃料収入を得ることができます。
また、入居者募集やクレーム対応、建物管理をサブリース会社が代行するため、管理の手間や負担が大幅に軽減されます。
デメリットとしては、賃料が満室想定の85%と低く設定されるため、
自主管理に比べて収益性が下がる点が挙げられます。
また、途中解約が難しく、オーナーが自由に入居者を選べないなど、経営の自由度が制限される点にも注意が必要です。
FP業務では、色々な専門職業家と連携することもあると思いますが、
今回のケースで関与する、専門職業家には、どのような方々がいますか?
不動産の取引に関する、課税上の具体的な税務相談は、税理士に、
売買契約等における、宅地建物取引業法に規定する業務については、宅地建物取引士に、
土地の所有権移転登記については、司法書士に、
正確な測量と境界の明示、登記については土地家屋調査士に、
測量に基づく適正な不動産価格の算定は不動産鑑定士と連携します。
質問は以上です。お疲れさまでした。
ありがとうございました。失礼いたします。
今回の設例は、不動産の有効活用、賃貸アパート経営、事業用定期借地権、サブリース契約に関する設例でした。
不動産の有効活用に関する設例は頻出です。
6種類の活用方法(自己建設方式、事業受託方式、土地信託方式、等価交換方式、定期借地権方式、建設協力金方式)は学科試験でも勉強したと思います。
実技試験では丸暗記ではなく、それぞれの違いを説明できるスキルが必要です。
FP1級実技試験の難しさは「自分の言葉で相手に伝える」ことだと思います。何度も声に出して読んだり、二人で読み合わせをするなど、お客様に説明するように話してみるのも効果的です。
最後まで諦めずに、FP1級学科試験合格者としての実力を発揮できるように頑張りましょう!
ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、FP1級技能士試験のご参考になれば幸いです。