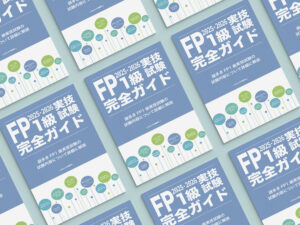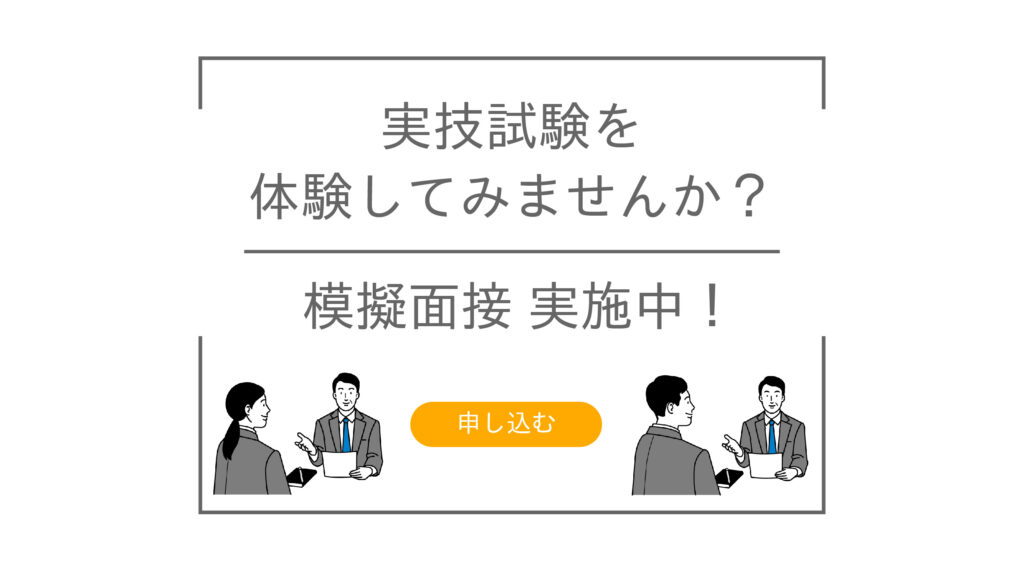【FP1級実技試験対策】土地の有効活用5つの代表手法と具体事例をわかりやすく解説
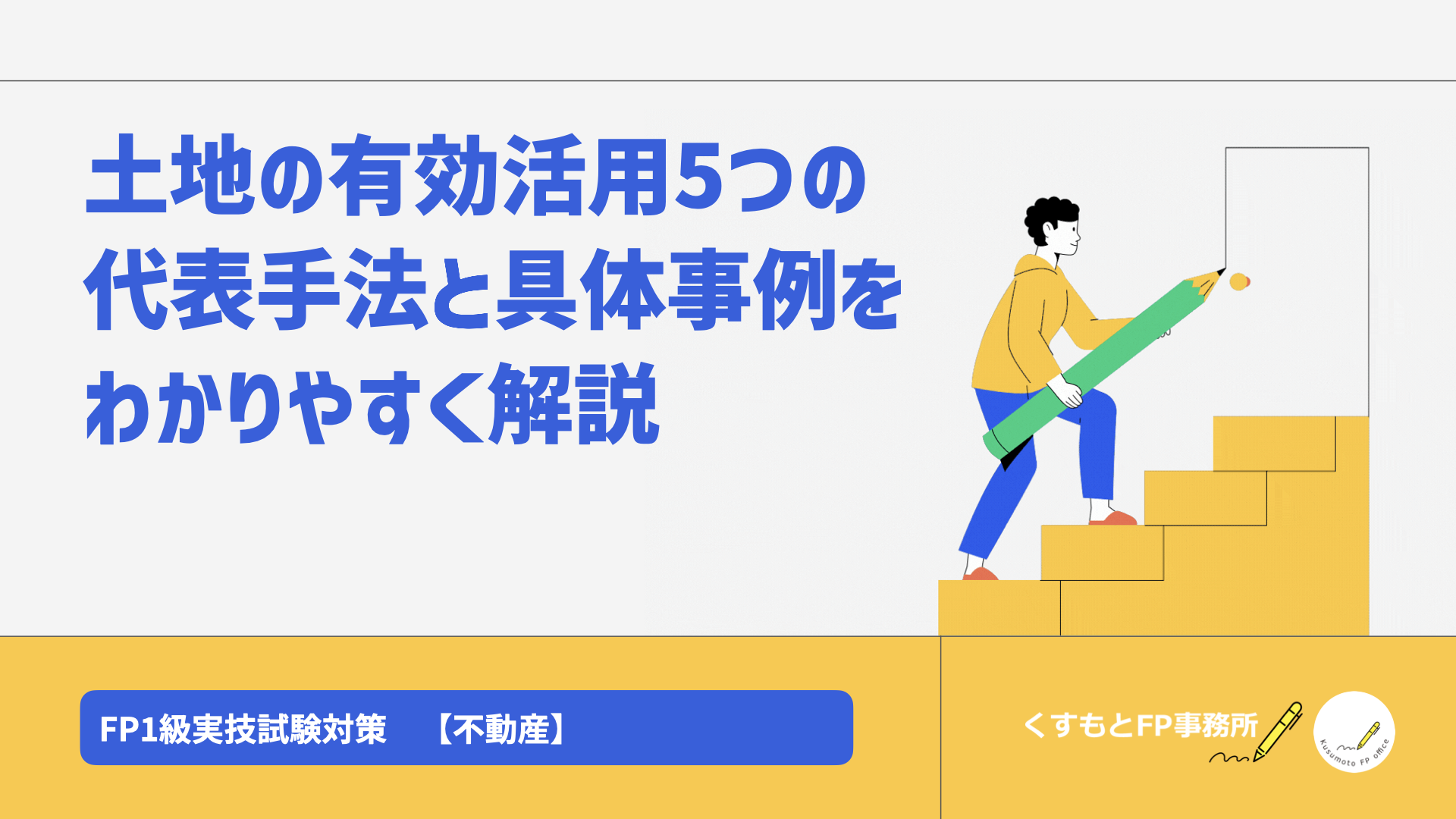
土地活用は、FPとして顧客に提案するうえで重要な知識のひとつ。特にFP1級実技試験では、不動産分野で頻出のテーマです。
この記事では、代表的な土地活用の5つの手法を、具体的な事例とともにわかりやすく解説し、試験対策や実務で役立つポイントをまとめました
実技試験での得点力アップを目指す方、必見です。

目次
この記事でわかること
- 土地の有効活用5つの代表的手法と特徴
- それぞれの活用事例と導入のメリット・注意点
- FP1級実技試験ではどう出題される?
- FP1級実技試験に向けたおすすめの勉強法

建設協力金方式|初期費用を抑えて建物を建てる
建設協力金方式は、将来的に建物を借りるテナントなどから建設協力金(保証金)を受け取り、それを建設費用に充てる方式です。
事例:駅前にある土地を有効活用し、ドラッグストアを誘致
- 土地所有者Aさんは、空き地のまま放置していた駅前の土地にドラッグストアチェーンを誘致。
- 建設協力金として5,000万円を受け取り、それを元手に建物を建設。
- 毎月の賃料から返済を行い、将来的に家賃収入で安定収益を確保。
メリットと注意点
- 初期費用が抑えられる
- 土地は貸家建付地、建物は貸家として評価され、評価額が低くなる可能性がある
- 建設協力金は、相続税の計算において債務控除の対象となる場合がある
- 建物はオーナーの所有物となるため、固定資産税はオーナーの負担となる
- 建物の修繕費や将来の建物の解体費用もオーナーの負担となる
- 事業主が撤退した場合、建物の活用方法を検討する必要がある
- テナントの信用力と契約内容がリスク管理の鍵

等価交換方式|土地を提供し資産価値を得る
等価交換方式は、土地の一部を提供し、その代わりに建物の一部を取得する方式です。
事例:築古アパートを解体し、分譲マンションに
- 土地所有者Bさんは、老朽化したアパートを取り壊し、不動産会社に土地の一部を提供。
- 開発会社が建てた分譲マンションの1階部分(店舗3区画)を取得。
- 家賃収入で毎月の収入を確保しつつ、相続対策にも活用。
メリットと注意点
- 資金負担なしで新築物件を取得可能
- 要件を満たすと「立体買換えの特例」により、譲渡所得税を繰延られる
- 土地は貸家建付地、建物は借家権割合を差し引いて評価され、評価額が低くなる可能性がある
- 部屋数や床面積に応じて分割することができ、遺産分割協議が円滑に進む可能性がある
- 提供した土地の所有権が失われる
- 交換であっても、不動産取得税や登録免許税などが課税される
- 価値の査定や共有部分の管理ルールに注意

定期借地権方式|安定収入を得ながら土地を守る
定期借地権方式は、土地の所有権を移転せず、一定期間だけ土地を貸し出す仕組みです。
事例:50年間の定期借地で大手ハウスメーカーと契約
- 相続で取得した土地所有者Cさんが、大手住宅メーカーに50年の定期借地。
- 借り入れをせずに土地活用が始められた。
- 地代は月額20万円、更新なしの契約で安定収入を得る。
メリットと注意点
- 一定期間で土地を返還してもらえる
- 長期間安定した地代収入を得られる
- 建物の建築費用が不要
- 宅地の定期借地の場合、相続税の課税時期における残存期間に応じて、土地の評価額が減額される
- 土地が宅地として活用されていると、固定資産税や都市計画税が軽減される
- 維持管理費用・手間が不要
- 存続期間中は土地を返還してもらえない
- 返還時の整地義務や契約条件に注意

土地信託方式|プロに任せて安定運用
土地信託方式では、土地を信託銀行などに名義移転し、プロに管理・運用を任せる形になります。
事例:高齢の土地所有者が信託で賃貸ビル運営
- 相続を見据えたDさんが信託銀行に土地信託を依頼。
- 信託銀行がテナントビルを開発・運用、収益はDさんに配分。
- 相続開始後は、信託財産としてスムーズに相続対応。
メリットと注意点
- 専門的運用で収益最大化を図れる
- 賃貸型は契約期間終了後、土地だけでなく建てた建築物もセットになって返還される
- ノウハウがなくても土地活用できる
- 建物の建築費用が不要
- 信託受益権を売却できる
- 仲介手数料(信託報酬)が発生する
- 配当金が得られない場合がある
- 損失があった場合は土地所有者が負担する

サブリース方式|空室リスクを軽減できる
サブリース方式は、不動産業者に一括で賃貸し、転貸によって家賃収入を得る方式です。
事例:地方都市でアパート経営に初挑戦
- Eさんが相続した空き地にアパートを建築。
- 管理の手間を減らすため、地元不動産会社とサブリース契約。
- 空室時でも一定の賃料を得られ、安心して運用できた。
メリットと注意点
- 管理不要で安定収入が得られる
- 土地は賃貸割合が常に100%の貸家建付地として評価され、評価額が低くなる可能性がある
- 一度契約すると、オーナー都合での解約が難しい場合がある
- サブリース会社が倒産した場合、家賃保証が受けられなくなる可能性がある
- 契約更新時の賃料見直しや途中解約リスクに注意

FP1級実技試験ではどう出題される?
FP1級実技試験(面接形式)では、以下のような観点から問われる可能性があります。
- 各手法の特徴とリスク比較
- 顧客のニーズに合った活用提案
- 所得税・相続税との関連性
- 建設協力金方式と事業用定期借地権方式のどちらを提案するか
つまり、単に用語を覚えるだけでは足りず、実務的な視点から、顧客対応力が求められます。
本気で合格を目指すあなたにおすすめの対策方法
土地活用のような実務テーマは、独学では理解しづらい部分も多く、体系的な学習が効果的です。
🎓 FP1級実技試験 模擬面接(オンライン対応)
試験本番と同じような設例・質問内容で、本番さながらの面接練習が可能です。
面接官経験者からのフィードバック付きで、「伝え方」や「論点整理」の力を高められます
📘 FP1級実技試験対策講座2025-2026
- 実技試験の出題傾向に沿った解説と問題演習
- 長期サポート型でじっくり実力をつけられる
- 過去問の解説だけでなく、「どう答えるべきか」にフォーカス
✅ まずは無料で対策の全体像を知りたい方へ
10日間にわたって、FP1級実技試験の合格ポイント・よくある失敗・勉強法を丁寧に解説した無料メールセミナーを配信しています。
✅ FP1級実技試験合格ナビ10日間無料メールセミナーはこちら

◆ まとめ|土地活用の知識はFP試験でも実務でも武器になる!
土地の有効活用は、資産の最大化・相続対策・安定収入の確保に欠かせないテーマです。
FP1級試験対策としても、実務スキルとしても、「わかる」から「説明できる」へ知識をレベルアップさせましょう!
合格に向けて一歩進みたい方は、以下の3ステップからスタートするのがおすすめです。
🎯 今すぐ合格への一歩を踏み出す
- 無料の10日間セミナーで全体像を把握する → 今すぐ無料登録
- 専門講座で知識と解答力を身につける → FP1級実技試験対策講座はこちら
- 模擬面接で本番対応力を鍛える → FP1級実技試験 模擬面接はこちら